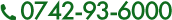旧耐震基準のマンションを選ぶ理由とリスク!リノベーションの可能性を探る | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売
旧耐震基準のマンションを選ぶ理由とリスク!リノベーションの可能性を探る

旧耐震基準のマンションは、地震リスクや資産価値の低下が懸念される一方で「あえて選ぶ人」もいます。
以下では、旧耐震基準について詳しくご紹介いたします。
1. 旧耐震基準マンションについて
旧耐震基準とは?基礎知識を押さえよう
中古マンションを購入する際、耐震基準は非常に重要なポイントです。
特に旧耐震基準と新耐震基準の違いや、それぞれの特徴を知っておくことで、安心して物件選びができるようになります。中古マンションの耐震基準は、建物が地震に対してどれくらい安全かを示す重要な要素です。
日本の耐震基準は、1981年に改正された「新耐震基準」以降、建物の耐震性が強化されました。このため、築年数や建設年によって耐震基準が異なります。
このセクションでは、旧耐震基準についての基礎知識を深め、関連する情報を詳しく解説します。

旧耐震基準と新耐震基準の違いとは
1. 新耐震基準(1981年6月1日施行)
1981年に改正された新耐震基準では、建物が地震の揺れに耐える能力が大きく強化されました。
新耐震基準が適用された建物は、比較的高い耐震性を持っており、大きな地震にも耐える設計となっています。したがって、1981年以降に建てられた中古マンションは、耐震性が高いと考えられます。

2. 旧耐震基準(1981年6月1日以前)
それ以前に建設されたマンションは「旧耐震基準」に基づいて設計されています。
この基準では、地震に対する強度が現在の基準よりも低く、安全性が不足している場合があります。特に1970年代以前に建てられたマンションは、耐震性に不安が残ることがあり、耐震補強を検討する必要があるかもしれません。
旧耐震基準とは、1981年5月31日以前に建築された建物に適用される耐震基準を指します。この基準では、震度5強程度の地震で倒壊しないことが求められていました。
一方で、1981年6月1日以降に制定された新耐震基準では、震度6強から7程度の地震にも耐えられる設計が求められるようになりました。
中古マンションの耐震基準を確認する際、この旧耐震基準と新耐震基準のどちらを満たしているかを把握することが非常に重要です。

旧耐震基準が適用されているマンションの築年数
旧耐震基準が適用されているマンションは、築年数が40年以上のものが主に該当します。
具体的には、1981年5月31日までに建築確認を受けた物件が対象です。したがって、購入を検討する中古マンションがこの年代に該当する場合は、耐震性の確認が不可欠となります。
ただし、1971年に耐震基準が一部改正されているため、この期間の物件でも耐震性に関して一定の注意が必要です。

旧耐震基準のマンションの耐震性能の実情
旧耐震基準のマンションの耐震性能は、新耐震基準を満たす物件と比較すると低いとされています。
しかし、設計の工夫や鉄筋コンクリートの使用量によって、一定の耐震性を備えている物件も存在します。
また、中古マンションの耐震基準を補うために耐震補強が施されているケースもあるため、具体的な性能については物件ごとに確認が必要です。

どのように耐震基準を確認するべきか
中古マンションの耐震基準を確認するには、いくつかの方法があります。
まずは、建築確認日を調べることで、旧耐震基準か新耐震基準のどちらが適用されているかを把握することが重要です。
また、建物の耐震性能を直接診断する耐震診断の結果を確認することも効果的です。さらに、住宅性能評価書やマンションの設計図をチェックすることで、耐震性についての情報を得ることができます。
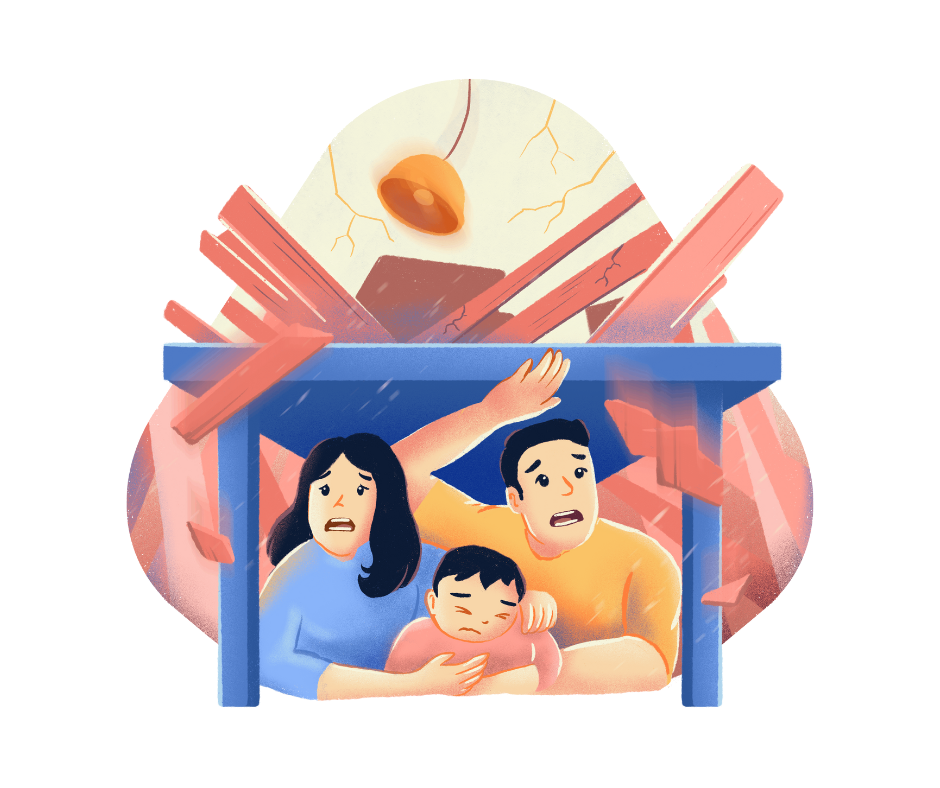
これらを総合的に検討することで、安全性の高い物件選びが可能となります。
建築確認書類の確認:建物が建設された年や使用された耐震基準が記載されています。
管理組合や売主に確認:管理規約や報告書で、耐震基準や過去に行われた耐震診断・補強工事について確認できます。

2. 旧耐震基準のマンションを選ぶメリット
購入価格が比較的安い
旧耐震基準のマンションは、新耐震基準が適用されているマンションに比べて購入価格が安いケースが多くあります。
これには、1981年以前に建設された建物が対象となるため、耐震性に対する不安を感じる方が一部存在することが影響しています。
しかし、その分、初期費用を抑えて購入を検討したい方には魅力的な選択肢となるでしょう。
たとえば、築20年以上の中古マンションでは価格が新築時の大幅に下がる傾向があるため、予算を抑えながら物件を手に入れることが可能です。

リノベーションの自由度が高い
旧耐震基準のマンションは、築年数が経過しているために室内のリノベーションが検討されることが多く、その自由度が高い点がメリットです。
建築当時の仕様は現代に比べてシンプルな間取りのものが多く、現在のライフスタイルに合わせて最適化する余地が大きいのが特徴です。
また、リノベーションを行いながら最新の設備を導入したり、個性的なデザインを採用したりすることで、住む人のライフスタイルに合った空間を実現できます。
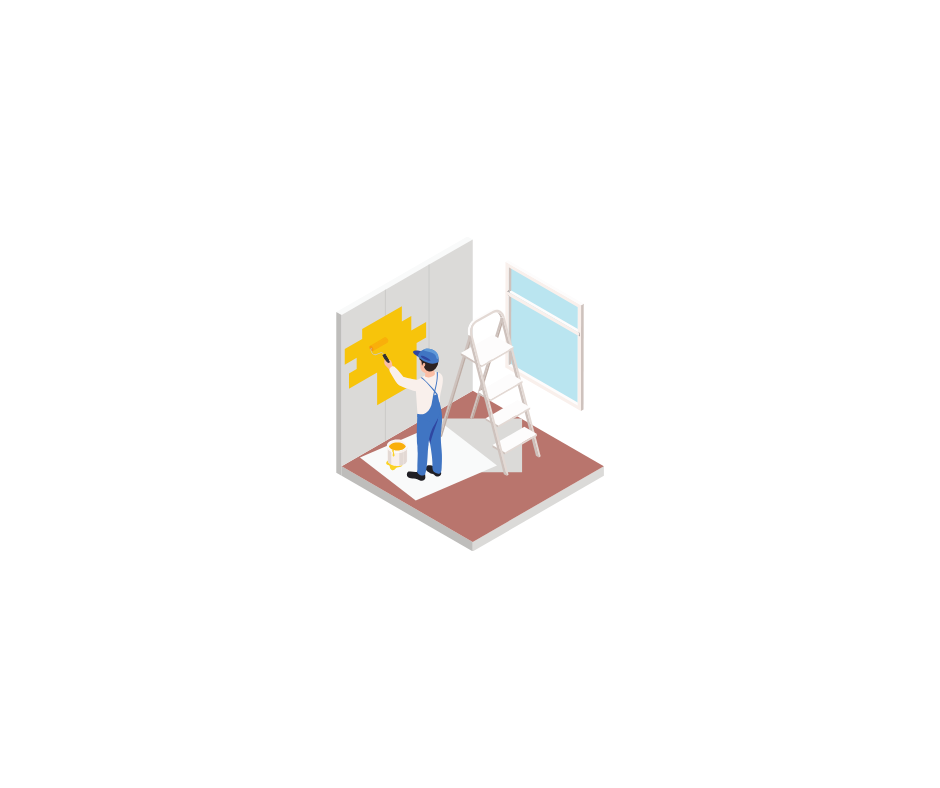
立地条件が良い場合が多い
旧耐震基準が適用されているマンションは、人口が増加した高度経済成長期から建設されたものも多く、都市部や駅近くなどの好立地に建てられている場合がよく見られます。
当時は都市計画が進行する中で利便性の高い場所にマンションが建設されており、現在でも交通アクセスや周辺環境の良さが評価されることがあります。こうした立地の魅力は、築年数が経過しても変わらない大きな資産価値とも言えるでしょう。
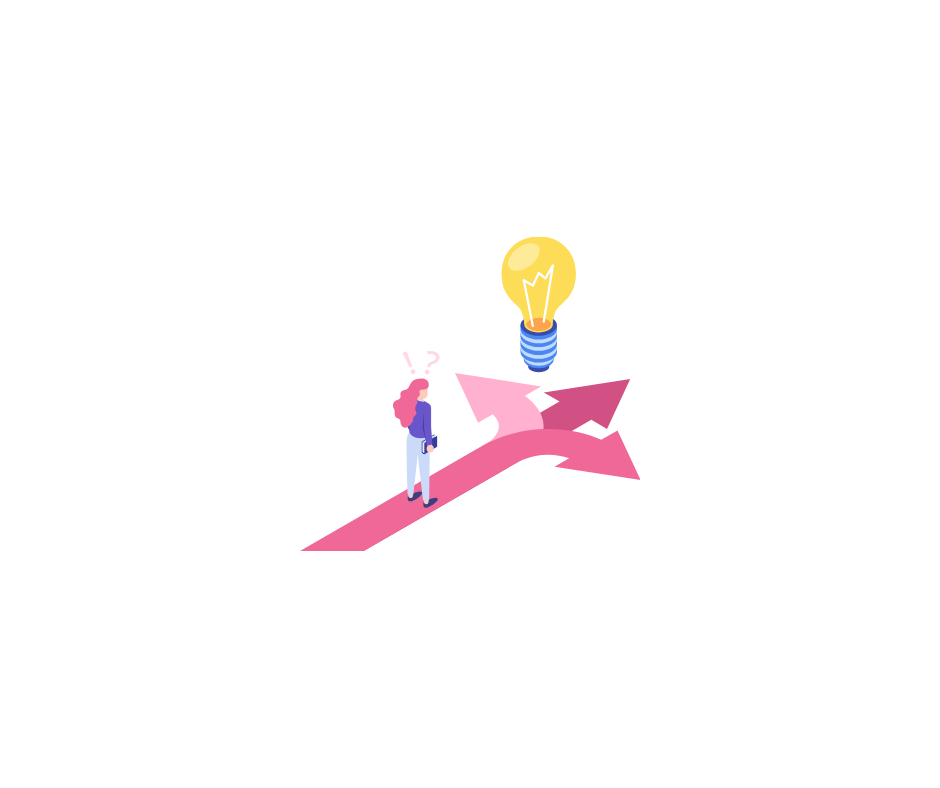
物件の選択肢が広がる
旧耐震基準のマンションを検討することで、物件の選択肢が大幅に広がるのも大きなメリットです。
現在の住宅市場では新築物件が限られている一方で、中古マンション市場のほうが圧倒的に多くの物件から選ぶことができます。
特に築30年〜40年程度のマンションの中には、建物の管理状態がしっかりしているものも多く、条件次第では価格や立地などの面で魅力的な選択肢となる場合があります。これにより、自分の希望により近い物件を見つける可能性が高くなります。

3.リスクと対策:旧耐震基準マンションの注意点
なぜ旧耐震基準は危ないのか?
✅1971年の改正をベースとし、「中規模自身(地震5程度)に耐えればよい」いう考えかた。
✅震度6強~7の大地震を想定していない。
✅建物の損傷よりも「人命を守る」ことが目的だったため倒壊は免れない可能性がある。
地震へのリスクとその低減方法
旧耐震基準が適用されているマンションは、震度5強程度の揺れに耐える設計基準となっています。
そのため、新耐震基準で定められた震度6~7の大地震には倒壊のリスクが高まる可能性があります。このようなリスクを低減するためには、耐震診断の実施が重要です。耐震診断を受けると建物の耐震性能が明確になり、必要に応じて耐震補強を行うことで安全性を向上させることができます。
また、マンション全体の管理組合が耐震補強工事の検討を進めている場合、積極的に参加し、管理体制の改善を図りましょう。
倒壊リスクが高まる要因
①コンクリートの劣化
✅築40年以上が多く、鉄筋コンクリートの中性化が進行。
✅中性化いより鉄筋が錆び、内部からひび割れ→構造強度の低下へ・
②耐震壁や柱の配置不足
✅耐震壁(地震力に抵抗する壁)が少なく、横揺れに弱い構造のものが多い
✅特に1階部分が駐車場などの「ピロティ構造」は倒壊リスクが高い。
③地盤との関係
✅旧耐震時代は地盤調査が不十分なケースもあり、液状化や不同沈下で倒壊リスクが高まることも
実際の地震でどうだったか?
◆阪神・淡路大震災(1995年)
✅旧耐震基準の建物が多数倒壊。死者の8割が建物倒壊による圧死。
✅新耐震基準の建物は、外壁が壊れる程度で倒壊はごく一部だった。
◆熊本地震(2016年)
✅旧耐震の木造住宅や集合住宅に倒壊が集中。
✅震度7が2回連続で起こったことで、弱点のある建物が再度揺られて倒壊。
4. 住宅ローン減税の適用条件を確認
旧耐震基準のマンションを購入する場合、住宅ローン減税が適用されるかどうかが特に重要です。
住宅ローン減税が適用される条件の1つとして「耐震基準を満たしていること」が求められるため、購入対象の中古マンションが新耐震基準を満たしているか、または耐震補強を行った実績があるかを確認する必要があります。
購入前に住宅性能評価書の有無や耐震診断の履歴をチェックし、適用要件を満たしていることを明確にしておきましょう。
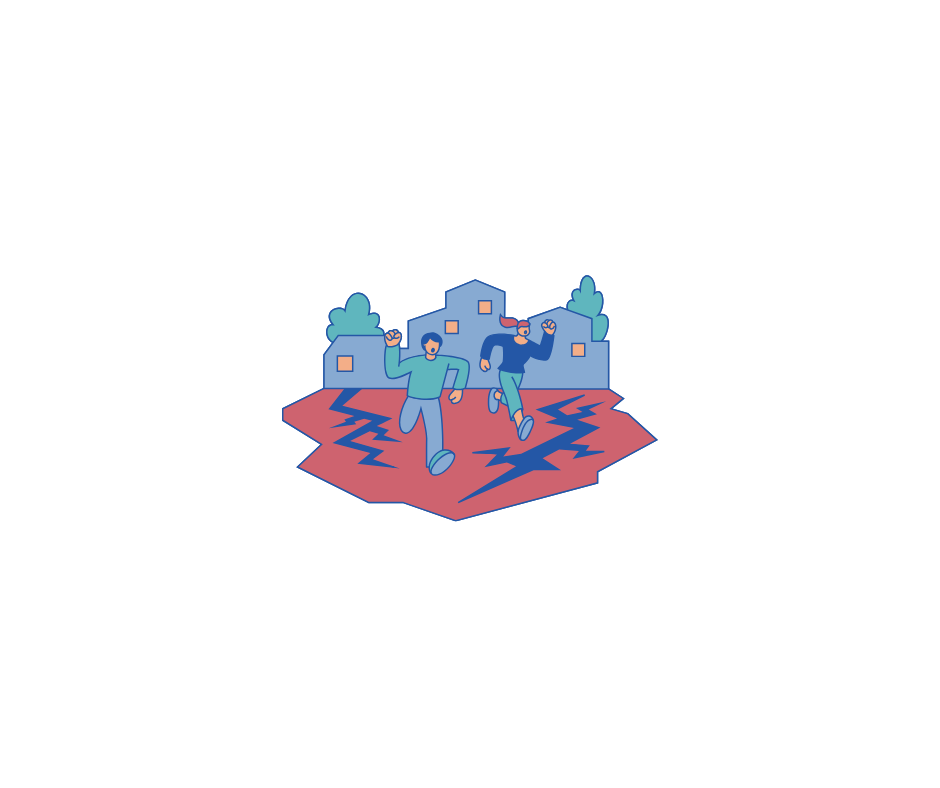
管理体制の重要性を見極めるポイント
旧耐震基準のマンションにおいては、建物の管理状況が耐震性や資産価値を左右する重要な要素です。管理組合が機能しており、修繕積立金が適切に運用されているかを確認することが大切です。
また、建物の共用部分が過去に適切なメンテナンスを受けていたかをチェックしましょう。
具体的には、定期的な大規模修繕の履歴や、建物診断報告書が揃っているかを確認すると良いです。
これにより、将来的な地震リスクに対する管理体制の信頼性が測れます。
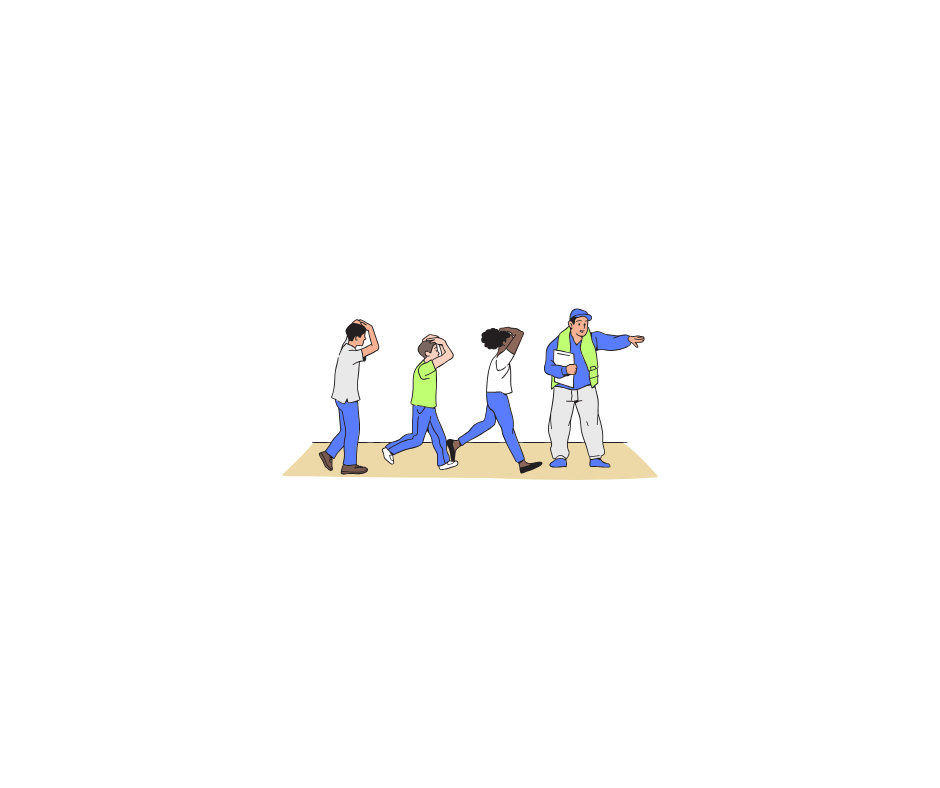
リノベーション時の注意事項
旧耐震基準のマンションをリノベーションする際には、耐震基準をクリアしていない部位がある可能性を考慮する必要があります。
間取り変更や内装の更新を行う際、耐震壁や構造部分に影響を与えない設計を心がけるべきです。
また、耐震補強工事を同時に行う場合には、設計士や施工業者に十分に相談し、安全性を確保する計画を立てましょう。
さらに、中古マンションの耐震基準に関する情報を購入者にも説明できるよう、リノベーションの内容や経緯をしっかり記録しておくことをおすすめします。

5. 旧耐震マンションのリノベーションで広がる可能性
リノベーションによる耐震補強の可能性
旧耐震基準のマンションでも、リノベーションによって耐震性能を向上させることが可能です。
具体的には、耐震補強工事を行うことで、建物全体の安全性を高めることができます。
例えば、鉄筋や鉄骨の補強、壁の補強材の追加などの方法が用いられます。
また、耐震性の向上が実現すれば、中古マンションの価値自体を高めることができるため、将来的な売却や投資にも有利になります。
さらに、住宅性能評価書などを活用して耐震等級をアピールすることで、安心感を提供することも可能です。

住みやすい間取り変更への対応
旧耐震基準の中古マンションは、リノベーションにより住みやすい間取りへ変更する自由度が高い点が魅力です。新築物件とは異なり、既存の間取りにとらわれず、家族構成やライフスタイルに合った空間デザインを実現することができます。
例えば、広々としたリビングを作ったり、キッチンの配置を変更することで、より快適な生活環境を整えることが可能です。特に、一人暮らしからファミリー層まで幅広いニーズを満たす間取り変更は、中古マンションリノベーションの一つの大きな強みです。

最新の設備を導入し快適に
旧耐震基準のマンションでも、リノベーションによって最新の設備を導入することで、快適な住環境を作ることができます。
例えば、省エネ性能の高いエアコンや床暖房、浄水機能のついた最新型のキッチンなどを取り入れることで、日々の暮らしがより便利になります。
また、スマートホーム技術を活用して、自動照明や遠隔操作による家電管理を導入することも可能です。これにより、古い物件でありながら、設備面で新築物件以上の快適さを実現できます。

投資物件としての活用例
旧耐震基準のマンションは、リノベーションによって投資物件としての価値を高めることもできます。
価格が比較的安いことから初期投資を抑えられるうえ、リノベーションすることで賃貸需要を高めることが可能です。
例えば、近年注目されているデザイナーズ物件やシェアハウスとしてリノベーションすることで、若い世代や働く単身者をターゲットに賃貸運用を行うケースがあります。
また、耐震補強を行った上で高収益を期待できる物件に仕上げることもできます。こうした工夫によって、旧耐震基準の中古マンションに新たな活用可能性が生まれるのです。

6. まとめ
近年では、耐震補強を施したマンションも増えており、地震への耐性を向上させるための工事が行われることがあります。このようなマンションはより安全に住むことができます。
中古マンションを購入するさいは、耐震基準や耐震性についてしっかりと確認し、必要であれば耐震診断を受けることをおすすめします。
執筆者名:丸山不動産販売 編集部
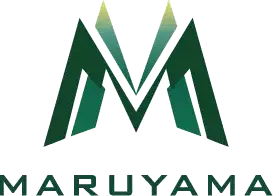
丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。
お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが
プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!
是非お気軽にご相談ください!
ページ作成日 2025-06-01
- 「親の家を売るなんて…」迷ったあなたへ。相続不動産で後悔しない選択とは?
- 奈良の不動産購入で「失敗しない」ための完全ガイド!流れと注意点を徹底解説
- 「まだ売れない…」と悩むあなたへ:不動産売却が長引く理由を徹底解説!最適な売却時期とタイミングを見極める方法
- 【奈良県で売却】不動産売却のタイミングと売却時期を徹底解説!スムーズな取引を実現するステップガイド
- 奈良市の不動産会社が解説!不動産の売却時期はいつがベスト?住み替えを後悔しないためのタイミング戦略
- 【奈良県の不動産売却】失敗しない不動産売却「売却時期」と「タイミング」
- 「離婚」で損しない!不動産売却の最適な「タイミング」と注意すべき「売却時期」
- 奈良の不動産屋が解説|初めての不動産売却 成功のポイントとよくある失敗例を徹底解説!
- 「知らなかった!」不動産売却時のライフライン解約・最適なタイミング|奈良市の不動産会社が解説!
- 家を売却する前にリフォームすべき?リフォームについて解説!
- もっとみる

 0742-93-6000
0742-93-6000