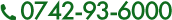身代わり申に秘められた奈良町のパワースポットの秘密 | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売
身代わり申に秘められた奈良町のパワースポットの秘密

奈良町に行くと一度は見たことがあるであろう吊るされている「赤い人形」。
これは奈良県に伝わる災厄除けのお守りで「身代わり申(みがわりさる)」といいます。今回は身代わり申についてご紹介いたします。
1. 身代わり申とは?その歴史と由来
庚申信仰と身代わり申の関係
身代わり申は、奈良町に伝わる赤い猿の人形で、「庚申信仰」に深く根付いたお守りです。
庚申信仰とは、60日に一度訪れる「庚申の日」に由来する信仰で、人間の体内にいるとされる「三尸の虫」が天帝に悪行を報告することで健康や運勢に悪影響が及ぶと信じられています。
この信仰において、三尸の虫を退治するための祭事が行われ、その象徴として作られたのがこの身代わり申です。災厄や病魔を遠ざける青面金剛の使いとして、また魔除けのお守りとして、大切にされています。
*三尸の虫*
「人間の体内に潜む三匹の悪い虫」とされる存在で、特に寿命・健康・道徳的な堕落に関わると信じられていました。
〈起源〉
古代中国の道教思想に由来します。
道教では、人の体には「三魂七魂(さんこんしちはく)」のように、霊的な存在が複数宿ると考えられていました。
その中で、「三尸虫」だけは人に害を与える存在とされました。

奈良町に伝わる庚申信仰の歴史
奈良町は、古来より庚申信仰が根強く残る地域の一つです。
この信仰は室町時代から江戸時代にかけて広まり、奈良町では庚申堂が祭事の中心となってきました。
庚申堂では、青面金剛像が祀られ、人々は悪運を払うために祈りを捧げました。
こうした信仰が日常生活にも浸透し、家庭でも庚申信仰を象徴するお守りとして身代わり申が広まりました。
奈良町の商家や一般家庭の軒先に吊るされた身代わり申は、地域を守るシンボルであり、町全体に庚申信仰の歴史的な痕跡が色濃く残っています。

身代わり申が赤色である理由
身代わり申が赤色で作られている理由には、古来より赤色が魔除けの力を持つとされてきたことが挙げられます。
赤は血の色に例えられ、不浄や災厄を防ぐ色として信仰されてきました。
また、赤色には活力や生命力の象徴という意味もあり、大切な家族の健康や幸運を願う想いが込められています。
赤い身代わり申が軒先に吊るされる光景は、奈良町特有の伝統文化として街を彩っています。
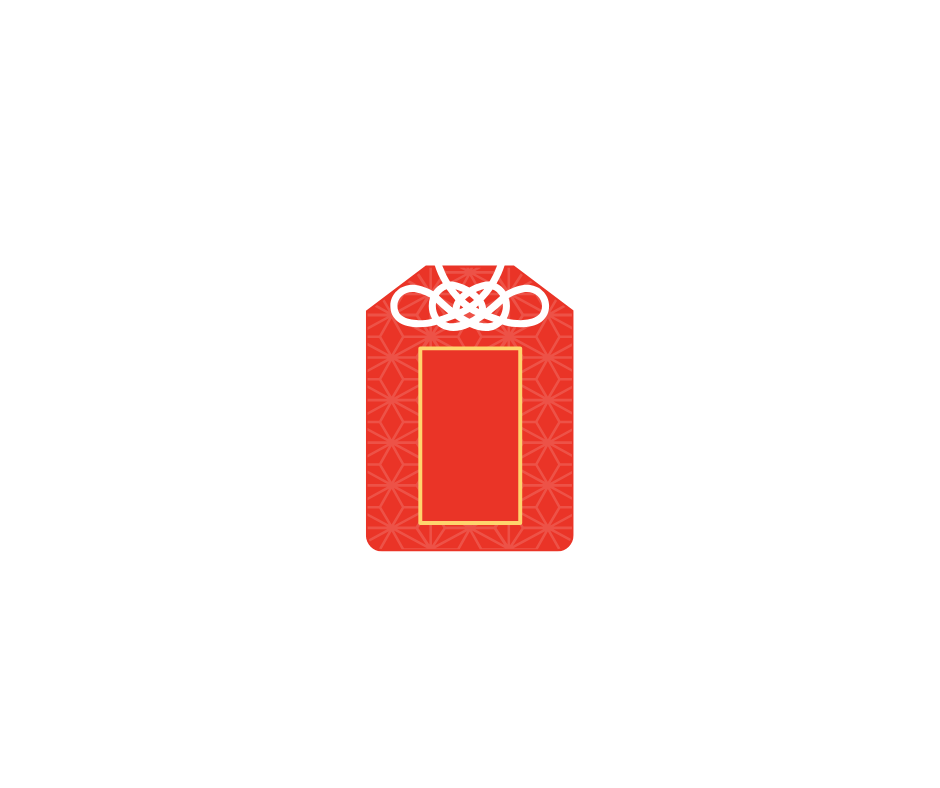
身代わり申と中国由来の文化
庚申信仰や身代わり申の文化は、中国から伝来した思想や風習が基になっています。
特に「庚申」の概念は中国の道教の影響を受けており、日本においては仏教や民間信仰と融合しながら独自の形で発展しました。
猿は、中国文化では除災招福を象徴する動物ともされ、日本でも神聖な存在として位置づけられています。
このように、身代わり申は中華由来の文化を受け継ぎながら、日本独自の形に昇華された象徴と言えるでしょう。
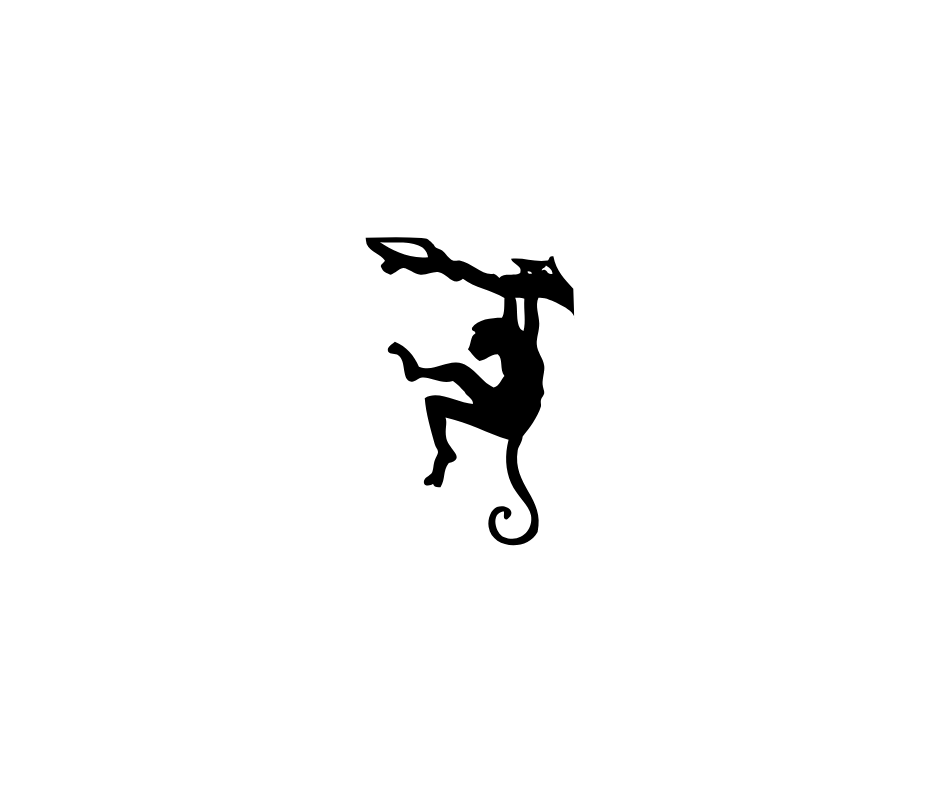
飛騨高山のさるぼぼとの共通点
奈良町の身代わり申と、岐阜県飛騨高山で知られる「さるぼぼ」には、いくつかの共通点があります。
どちらも猿をモチーフとした赤い人形であり、家族の健康や幸福を願うお守りとして位置付けられています。
さらに、どちらも災厄を防ぐ目的で家庭や地域に根付いた文化的存在です。さるぼぼが子どもの健やかな成長を願う象徴であるのに対し、身代わり申は災厄を代わりに受けてくれる存在として信じられています。
それぞれの地域の特色を反映しながらも、共通の願いを持つ点に、日本の民間信仰の豊かさを感じることができます。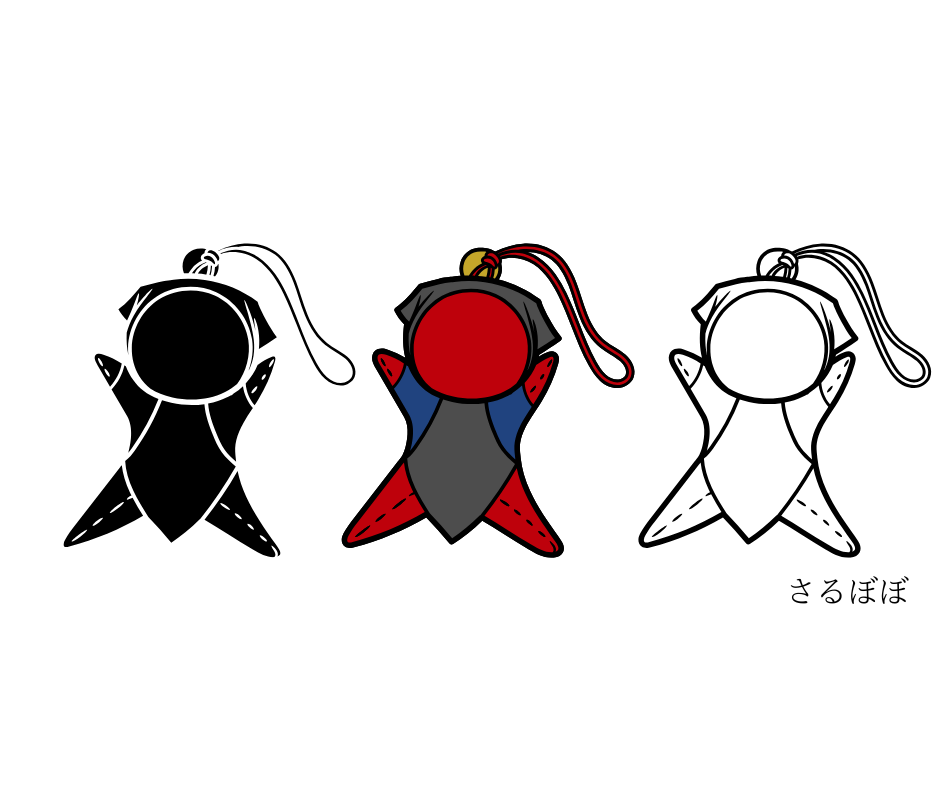
2. 身代わり申がもたらす効果と信仰
魔除けとしての役割
身代わり申については、古くから魔除けとしての役割が期待されています。
その赤い色は、災いを遠ざける力があるとされ、厄除けの象徴とされています。また、家の軒先などに吊るすことで、外部からの邪気や悪いエネルギーを防ぐと信じられてきました。
こうした信仰は、庚申信仰に基づく日本ならではの文化の一端を感じることができます。
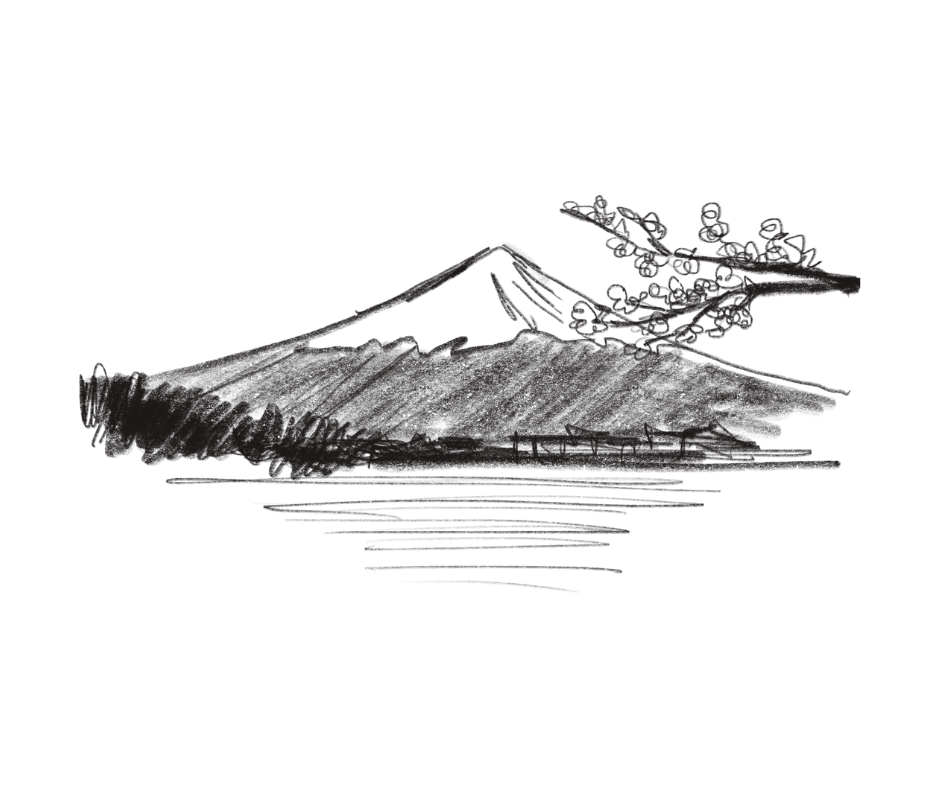
災厄を代わりに受けると信じられる理由
身代わり申は、その名前の通り、自らが災厄を代わりに受けてくれる存在とされています。
庚申信仰において、青面金剛の使いとされる猿が、人々を災厄から守ってくれるという考えに基づいています。
赤い猿の形をしたお守りは、その場に置かれた人や家族の代わりに悪い出来事を引き受け、持ち主を守ると考えられています。

願いごとを叶える「願い申」としての信仰
身代わり申は魔除けの象徴であると同時に、願い事を叶える「願い申」としての信仰もあります。
特に身代わり申を吊るした際には、その中心に願い事を書いた紙を折りたたんで入れるという文化も存在します。こうした習慣により、単なるお守り以上の心のよりどころとして親しまれてきました。
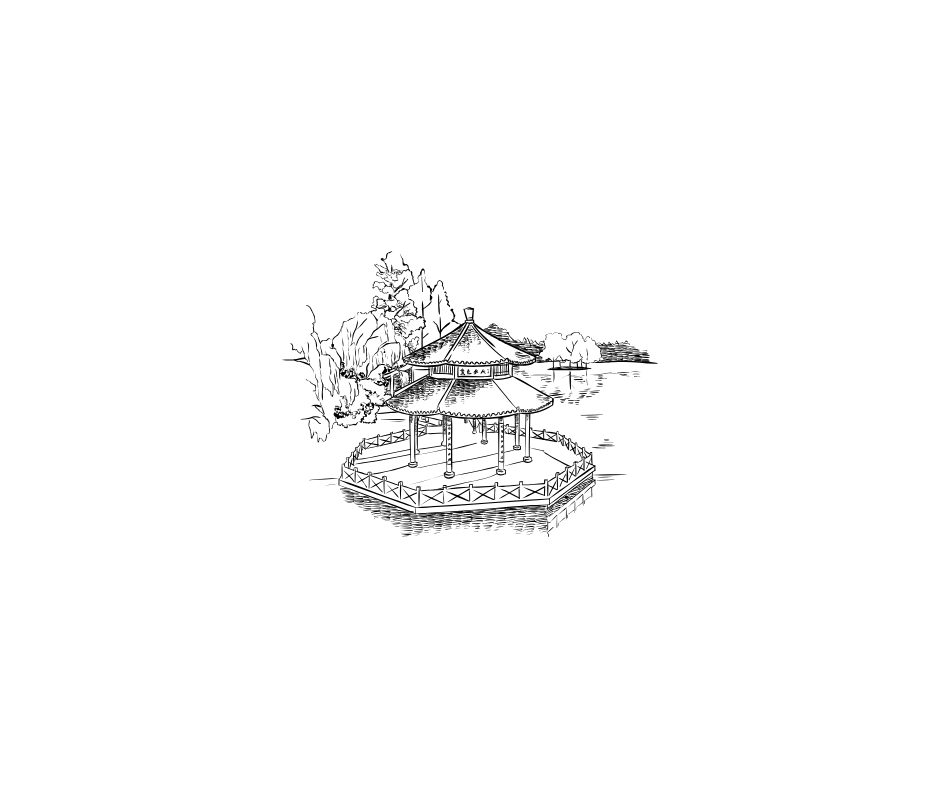
家族の健康を守るお守りとしての重要性
身代わり申は、家族の健康を守るお守りとしても大切にされています。
歴史的には、家族一人ひとりのための身代わり申を準備し、人数分吊るすという風習がありました。
現代では、家族一同の無病息災を祈って5つ並べることが多いですが、このように家族全体を守る存在として受け継がれていることがわかります。
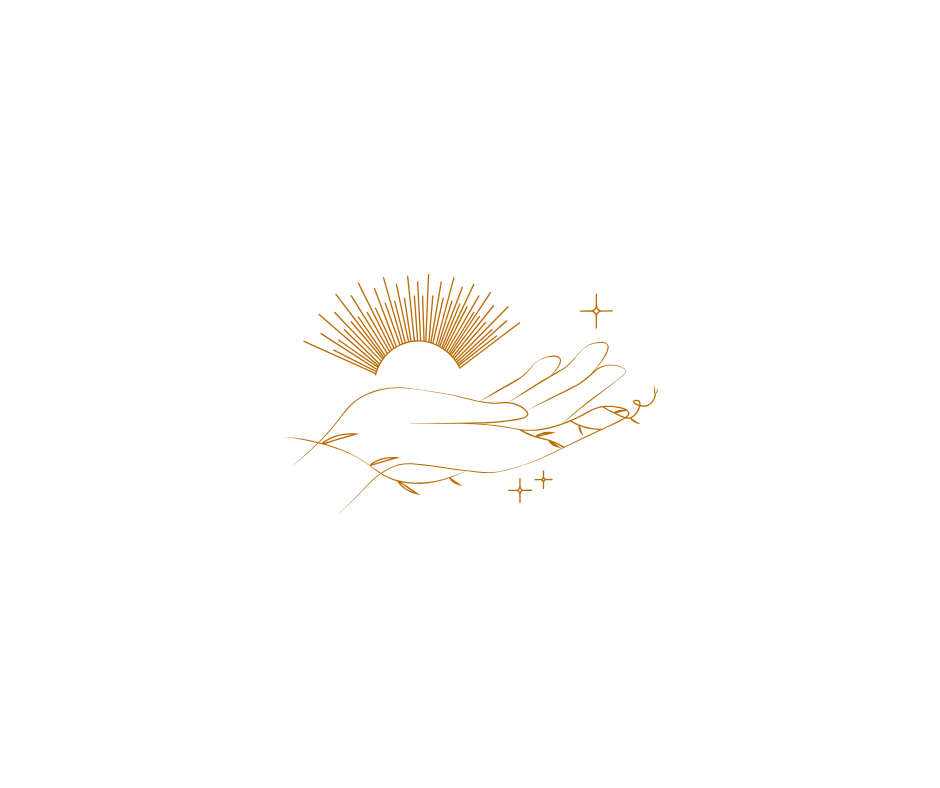
身代わり申が現代でも愛される理由
身代わり申が現代でも愛される理由には、その素朴なデザインと精神的な安心感が挙げられます。
また、奈良町の伝統ある文化を象徴する存在としても、観光客や地元の人々に親しまれています。装飾としてもかわいらしく、日常生活に取り入れやすいため、時代を問わず多くの人に愛用されています。
さらに、手作り体験や購入スポットを通じて、身代わり申を生活に取り入れる文化が広がり続けている点も、その大きな魅力の一つです。

3. 奈良町の景観と身代わり申の関係性
身代わり申が軒先に吊るされる意味
奈良町の街並みを歩くと、多くの家の軒先に赤い身代わり申が吊るされている光景を目にすることができます。
この風習は、庚申信仰に基づいて災厄を防ぎ、家族の安泰を願うものです。かつては家族の人数分吊るすのが一般的でしたが、現在では「ご縁」を象徴する数字として5つ吊るす家庭もあります。
この赤い人形が家を守り、災厄を代わりに受けてくれるという信仰が多くの人々に受け継がれています。

奈良町独特の景観としての価値
身代わり申は奈良町の景観に特別な彩りを添えています。軒先に吊り下げられた赤い小さな人形たちは、古い街並みの中でまるで町全体を見守る存在のように感じられます。
そんな風景は、庚申信仰の文化を今に伝えると同時に、奈良町の独特な雰囲気を形成しています。奈良町の風景に身代わり申が溶け込んでいることは、観光客にとっても新鮮な驚きであり、日本の伝統文化の奥深さを感じる一因となっています。
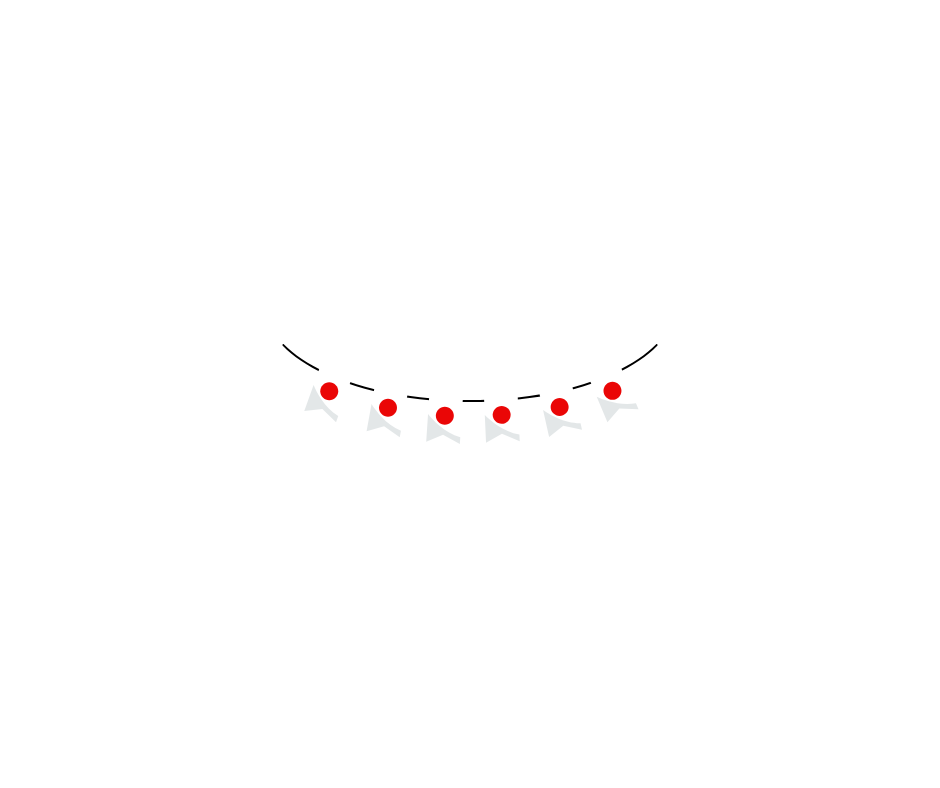
江戸時代の風情を感じるまち並み
奈良町の街並みには、江戸時代から続く古い町家が多く残っており、その趣ある姿が日本の歴史を今に伝えています。
これらの町家の軒先に吊るされた赤い身代わり申は、江戸時代の風情をより一層引き立てています。風雨に耐えながら残されてきた町家と身代わり申の組み合わせは、見ているだけで当時の生活や信仰の風景を想像させてくれます。

観光客にも人気の撮影スポット
奈良町を訪れる観光客にとって、軒先に揺れる赤い身代わり申は人気の撮影スポットとなっています。
そのかわいらしい姿だけでなく、背景にある深い歴史や信仰がその注目度をさらに高めています。
特に、奈良町の町家や石畳道との組み合わせは日本らしい風情を感じさせ、多くの観光客が写真を撮りに訪れています。
インスタグラムなどのSNSでも、身代わり申を紹介する投稿が増えており、その人気は年々高まっているようです。
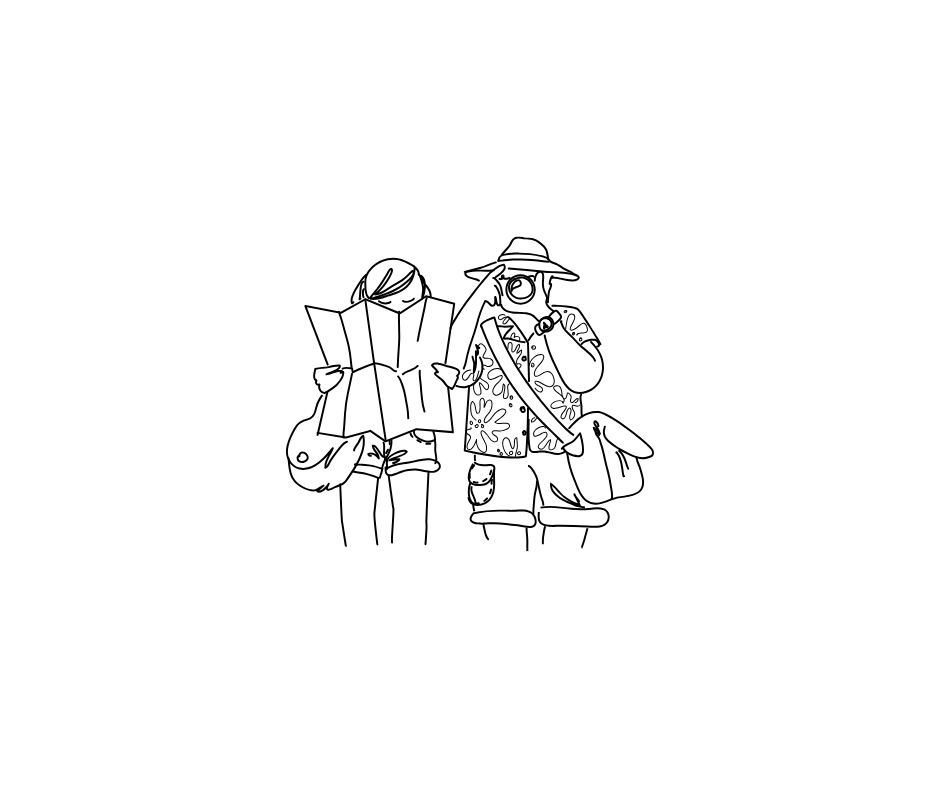
奈良町全体に広がる庚申信仰の痕跡
奈良町を散策していると、町全体に庚申信仰の痕跡を見て取ることができます。
軒先に吊るされた身代わり申のみならず、庚申堂や円形の青面金剛像が街中に点在しており、この地域に根付いた信仰の深さを感じることができます。
これらの庚申信仰に関連する風習や構築物は、奈良町の重要な文化財産の一つであり、現代でも地域住民だけでなく観光客を惹きつける大切な要素となっています。

4. 身代わり申を求めて奈良町を歩く
身代わり申を購入できるスポット
奈良町を訪れると、赤い人形である身代わり申を購入できるスポットがいくつか点在しています。
中でも奈良町資料館は代表的な場所で、ここではさまざまなサイズや形状の身代わり申が販売されています。
大きさは2㎝の小さなものから25㎝の立派なものまで揃っており、自分の好みや用途に合わせたものを選ぶことができます。
また、セット商品や根付タイプなども人気があり、観光客だけでなく地元の人々にも愛されています。特に「プチ三連」という商品は、かわいらしいサイズ感とお手頃な価格で評判となっています。
*奈良町資料館*
奈良町の路地を歩くと、ふと目に留まるのが小さな町家を活かした「奈良町資料館」
ここでは、日本の庶民文化や庚申信仰、そしてならまちに息づく伝統が温かく伝えられています。
設立:1985年、館長の自宅を改装し設立された施設資料館
入館料:無料
開館時間:10:00~16:00 火曜・水曜・木曜は休み(祝日は開館)
アクセス:奈良県奈良市西新屋町14-3
※2025年6月14日時点の情報
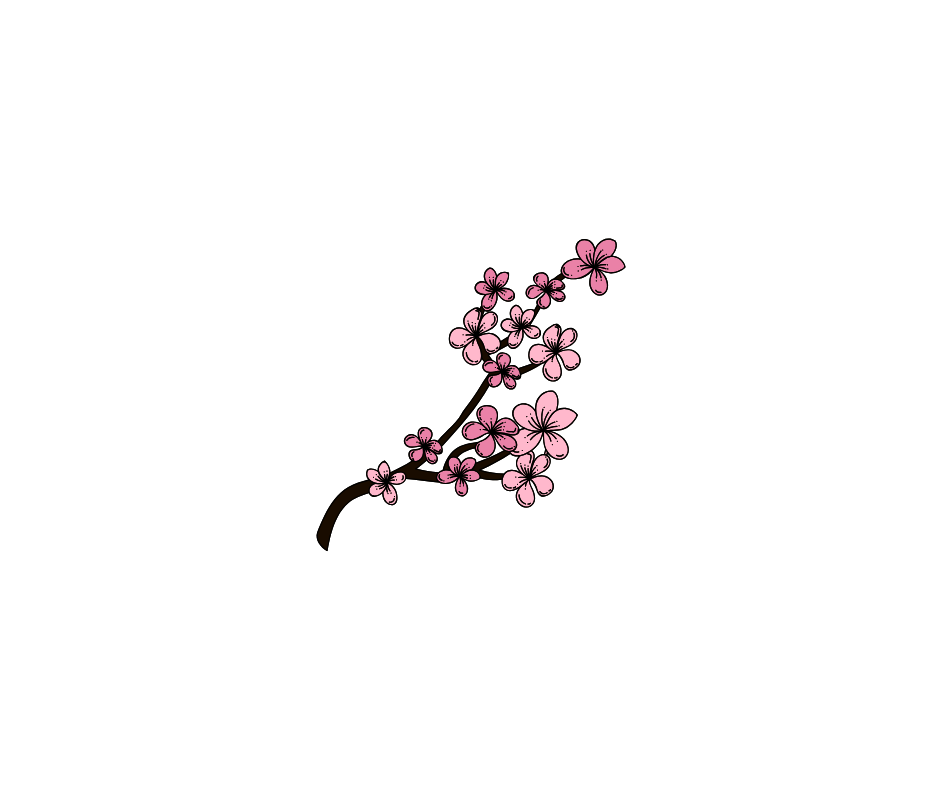
庚申堂を訪れる意味と体験
奈良町を歩く中でぜひ訪れてほしいのが庚申堂です。
ここでは身代わり申を吊るしている軒先を見るだけでなく、庚申信仰そのものに触れることができます。
庚申堂の本尊である青面金剛像とともに、身代わり申の由来や信仰の奥深さを体感することができます。庚申堂はその歴史的背景も興味深く、古くから地域の人々の祈りの場として親しまれてきました。
ここではお守りとして身代わり申を購入するだけでなく、心を落ち着けて祈りを捧げることができる特別な体験ができます。
◆奈良で有名な「身代わり申」の神社
庚申堂(こうしんどう)-奈良市高畑町
✅春日大社の近く、高畑町にある庚申信仰の拠点。
✅色とりどりの布製の「申」が軒先につるされているのが特徴。
✅この申は「災難の身代わり」として、1年守ってもらった後にお礼参りで納められます。
多くの観光客が訪れ「軒先に吊るされた申」がおしゃれで可愛いとSNSでも話題になりました。

心願成就を願う優しい習慣
奈良町では、身代わり申を通じて心願成就を願う優しい習慣が今も受け継がれています。
身代わり申は古来より魔除けや災厄を引き受けてくれるお守りとされており、家族や自身の健康、そして幸せを願う気持ちから家の軒先に吊るされています。
このような習慣は、現代においても多くの人々に支持され、特に庚申信仰に縁のある奈良町では日常の一部として根付いています。
願いを込めて吊るされた身代わり申には、持ち主の温かい祈りが込められており、その姿を見るだけで訪れる人の心を和ませてくれるでしょう。

身代わり申を手作りするワークショップの魅力
奈良町では身代わり申を手作りするワークショップも人気を集めています。
このワークショップでは、自分だけのオリジナル身代わり申を作ることができ、作る過程を通じて庚申信仰や伝統工芸の魅力を学ぶことができます。
初心者でも簡単に作れるよう丁寧に指導してもらえるため、小さなお子さまから大人まで幅広い層に楽しんでもらえます。
また、自分で作り上げた身代わり申には特別な思い入れが生まれるため、より一層お守りとしての価値を感じることができます。作り終えた後は、できあがったお守りと一緒に奈良町を散策する楽しみが待っています。

奈良町の散策ルートで目にする身代わり申
奈良町を歩くと、いたるところで赤い身代わり申が軒先に吊るされている光景を目にすることができます。
これらは災厄を防ぎ、幸せをもたらすとされ、地域の人々の信仰心を象徴しています。
特に観光ルートに組み込まれるエリアでは、町家特有の風情ある景観とともに身代わり申を見ることができ、写真映えするスポットとしても人気です。
こうした情緒あふれる風景は、明治や大正時代の風情をそのまま残した奈良町特有の魅力を際立たせています。
奈良町を訪れた際には、心を癒しながら散策を楽しみつつ、身代わり申が持つあたたかな雰囲気を味わってみてください。

5. まとめ
日本の庚申信仰(こうしんしんこう)に由来するお守りや風習で、災いや病気、厄を代わりに引き受けてくれる猿(申)の形をした守り神・人形である「身代わり申(みがわりさる)」
奈良町では、民家や店の軒先につるされているのが風物詩となっています。
江戸~明治の町家が残る歴史的景観の奈良町。
細い路地に格子戸が並ぶ風景はまるでタイムスリップしたような空間です。
身代わり申が吊るされた家が多く、ならまち独特の風景を是非足を運んで体験ください。
執筆者名:丸山不動産販売 編集部
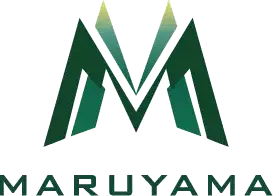
丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。
お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが
プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!
是非お気軽にご相談ください!
ページ作成日 2025-06-14
- 【奈良県で売却】不動産売却のタイミングと売却時期を徹底解説!スムーズな取引を実現するステップガイド
- 奈良市の不動産会社が解説!不動産の売却時期はいつがベスト?住み替えを後悔しないためのタイミング戦略
- 【奈良県の不動産売却】失敗しない不動産売却「売却時期」と「タイミング」
- 「離婚」で損しない!不動産売却の最適な「タイミング」と注意すべき「売却時期」
- 奈良の不動産屋が解説|初めての不動産売却 成功のポイントとよくある失敗例を徹底解説!
- 「知らなかった!」不動産売却時のライフライン解約・最適なタイミング|奈良市の不動産会社が解説!
- 家を売却する前にリフォームすべき?リフォームについて解説!
- 奈良市の不動産会社が解説|「共有持分」って何?初心者にもわかりやすい基礎知識とトラブルの実例
- 再建築不可って何?価格の安さの裏に隠された現実に迫る!
- 奈良の不動産会社が解説|底地と借地の違いを初心者向けにわかりやすく解説!
- もっとみる

 0742-93-6000
0742-93-6000