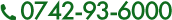不動産と税金の関係をわかりやすく解説|知らないと損する税の知識 | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売
不動産と税金の関係をわかりやすく解説|知らないと損する税の知識
_2.png)
不動産を所有・運用するにあたって、避けて通れないのが「税金」の問題です。
家を買ったり売ったりするタイミングは人生でそう何度もないため、税金についての知識が十分でないまま手続きを進めてしまい、後々後悔するケースも少なくありません。
不動産に関わる主な税金をわかりやすくご紹介します。
1.不動産に関する税金の全体像
◎不動産に関する税金
不動産に関する税金には、不動産取得税、登録免許税、印紙税、固定資産税、所得税などがあります。
_7.png)
◎国税と地方税
誰が課税するのかといった面から、税金が国税(国が課税)と地方税(地方公共団体が課税)に分かれます。
◆国税
①所得税:不動産を売却し、所得を得た時に課される税金
②登録免許税:不動産の登記等を受けるときに課される税金
③印紙税:不動産の売却契約書等を作成したときに課される税金
◆地方税
①不動産取得税:不動産を取得したときに課される税金
②固定資産税:不動産を保有していると課される税金
2. 不動産取得税
不動産を取得した場合(購入したときや増改築したとき)、不動産取得税がかかります。
なお、相続や法人の合併等によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の基本的な内容は次のとおりです。
不動産取得税の基本的な内容
◎課税主体 *誰が税金を課すのか?
⇒不動産がある都道府県(地方税)
◎納税義務者 *だれが税金を払うのか?
⇒不動産の取得者
◎課税主体 *何に対して税金がかかるのか?
⇒不動産の取得に対して税金がかかる
(有償・無償を問わない:具体的には、売買・交換・贈与・新築・改築などによる取得)
| 不動産の取得とみなされるもの |
①新築家屋の場合、最初の使用または 譲渡が行われた日に家屋の取得があったものとみなされる。 ②①の場合で、家屋が新築された日から6カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われないときは、6カ月を経過した日に家屋の取得があったものとみなされる。 |
◎非課税 *税金がかからない場合は?
⇒①取得者が国・地方公共団体等であるとき
②相続、法人の合併等によって不動産を取得したとき
◎課税標準 *税金の計算のベースとなる金額は?
⇒固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)
◎税金の計算 *税率はいくら?
⇒不動産取得税=固定資産税評価額×税率
税率⇒土地・住宅の場合:3%
住宅以外の建物の場合:4%
◎納付方法 *税金の納め方は?
⇒普通徴収
国や地方公共団体が税額を計算して、納税者に通知し、それにもとづいて納税者が税金を納付する方法
◆免税点
課税標準額が以下の場合には不動産取得税はかかりません。
免税点
◎土地:10万円未満
◎建物:①新築・増改築 1戸につき23万円未満
②その他(中古住宅の売買など) 1戸につき12万円未満
◆課税標準の特例
一定の不動産については、課税標準について次の特例があります。
課税標準の特例
◎宅地の課税標準の特例
宅地を取得した場合、課税標準額が1/2に引き下げられる
不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%
◎住宅の課税標準の特例
一定の住宅(建物)の場合、課税標準額から一定額を控除することができる
*新築住宅の場合*
不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円×1/2)×3%
| 要件 | ・床面積:50㎡(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40㎡)以上
240㎡以下 ・築年数:新築 ・その他:自己居住用も賃貸住宅も適用可能 法人も個人も可 |
*中古住宅の場合*
不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額×1/2)×3%
控除額⇒新築された時期によって異なる最大1,200万円)
| 耐震基準 適合既存住宅 の場合 |
要件 | ・床面積:50㎡(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40㎡)以上 240㎡以下 ・築年数:昭和57年1月1日以後に新築されたもの または 一定の耐震基準に適合するもの ・その他:個人が自己の居住用に取得したもの ⇒個人のみ可/賃貸住宅は適用不可 |
| 耐震基準 不適合既存住宅 の場合 |
要件 | ・床面積:50㎡(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40㎡)以上 240㎡以下 ・築年数:昭和56年12月31日以前に新築されたもの ・その他:平成26年4月1日以後に取得。取得後6カ月 以内に次の3つが行われていること。 ①耐震改修工事 ②工事後、耐震基準に適合している証明を受ける ③工事後、取得者が居住する |
3.登録免許税
登録免許税は、不動産の登記等をうけるときにかかる税金です。
◆登録免許税の基本的な内容
登録免許税の基本的な内容は次のとおりです。
登録免許税の基本的な内容
◎課税主体 *誰が税金をかすのか?
⇒国(国税)
◎納税義務者 *誰が税金を払うのか?
⇒登記を受けるもの
◎課税主体 *何に対して税金がかかるのか?
⇒不動産の登記に対して税金がかかる
◎非課税 *税金がかからない場合は?
⇒①国・地方公共団体等が自己の為に受ける登記
②表示に関する登記
◎課税標準 *税金の計算ベースと異なる金額は?
⇒固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)
(固定資産税評価額)⇒抵当権設定登記は債権金額
☆不動産の上に借地権などの所有権以外の権利が存在するときは、
その権利がないものとした価額となる(⇒更地価格)
◎納付方法 *税金の納め方は?
⇒現金納付(納付額が3万円以下の時は印紙納付も可能)
◆登録免許税の税率
登録免許税の税率は次のとおりです。
_9.png)
◆(一般)住宅用家屋の軽減税率の特例の適用要件
(一般)住宅用家屋の軽減税率の特例の適用要件
| 所有権保存登記 軽減税率:0.15% |
所有権移転登記 軽減税率:0.3% |
抵当権設定登記 軽減税率:0.1% |
|
| 適用要件 | ☆自己居住用であること ☆個人が受ける登記であること ☆家屋の床面積が50㎡以上であること ☆新築または取得後1年以内に登記を受けること 等… |
☆自己居住用であること ☆個人が受ける登記であること ☆家屋の床面積が50㎡以上であること ☆新築または取得後1年以内に登記を受けること 等… |
☆自己居住用であること ☆個人が受ける登記であること ☆家屋の床面積が50㎡以上であること ☆新築または取得後1年以内に登記を受けること 等… |
| 適用要件 | 新築住宅のみ 適用可能 |
既存住宅の場合は、 一定の耐震基準に適合 している家屋または 昭和57年1月1日以降に 建築された家屋であること |
既存住宅の場合は、 一定の耐震基準に適合 している家屋または 昭和57年1月1日以降に 建築された家屋であること |
4. 印紙税
印紙税は、一定の文書を作成した場合に課される税金(国税)で、契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税します。
一つの課税文書を二人以上で作成した場合には、連帯して納付する義務を負います。
◆印紙税の基本的な内容
印紙税の基本的な内容は次のとおりです。
印紙税の基本的な内容
◎課税主体 *誰が税金を課すのか?
⇒国(国税)
◎納税義務者 *誰が税金を払うのか?
⇒課税文書の作成者
◎課税客体 *何に対して税金がかかるのか?
⇒課税文書に対して税金がかかる
◎非課税 *税金がかからない場合は?
⇒国・地方公共団体等が作成する文書
例えば)個人と国等が共同で作成した文書の場合は、個人が保存している文書(国等が作成したもの)は非課税となるが、国等が保存している文書(個人が作成したもの)は課税される!
◎納付方法 *税金の納め方は?
⇒原則として、印紙を貼付して消印する方法によって納付
消印⇒消印は、課税文書の作成者だけでなく、代理人、使用人等の印鑑、省名によって行うことができる。
◆課税文書に該当するもの
課税文書には、一定の契約書、受取書(領収書)などが該当します。
課税文書に該当するもの
◎契約書
①不動産の譲渡に関する契約書
⇒不動産の売買契約書、土地交換契約書など
②地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書
⇒土地賃貸借契約書など
③消費賃借に関する契約書
⇒金銭消費賃貸借契約書など
④請負に関する契約書
⇒工事請負契約書など
| ちなみに課税文書に該当しない契約書は… |
| ①土地以外の賃借権の設定・譲渡に関する契約書 ⇒建物の賃貸借契約書など |
| ②抵当権、永小作権、地役権、質権の設定・譲渡に関する契約書 ⇒抵当権の設定契約書など |
| ③委託に関する契約書 ⇒媒介契約書、委任状など |
| ④使用賃借に関する契約書 |
*ポイント*
✅契約金額が1万円未満の契約書は原則非課税
✅一時的に作成する仮文書(後日、正式文書を作成するもの)であってもの、課税文書に該当する
✅同一内容の契約書を二通以上作成した場合は、各契約書に印紙税が課される。
◎受取書
⑤金銭等の受取書
⇒領収証
*ポイント*
✅記載された金額が5万円未満の受取証、営業に関しない受取書は非課税となる
例えば… 個人が自宅を売却した際の、売買代金が記載された受取書には印紙税が課税されない。
◆課税標準
印紙税の課税標準は、文書に記載された金額(記載金額=契約書の場合には契約金額、受取書の場合は受け取り金額)です。なお、契約金額の記載がない契約書についても印紙税が一律200円かかります。
不動産取引に関する具体的な記載金額は次のようになります。
記載金額(課税標準)
| 契約書 | 記載金額 |
| 売買契約書 | 売買代金 |
| 交換契約書 | 対象物の双方の金額が記載されているとき ⇒いずれか高い方 交換差金のみが記載されているとき ⇒その金額 |
| 贈与契約書 | 「記載金額のない契約書」として200円の印紙税が課される |
| 土地の 賃貸借契約書 |
契約に際して相手方に対して交付し、後日変換されることが予定されていない金額 ⇒地代、敷金は契約金額とかわらない |
| 変更契約書 | もとの契約書の契約金額と総額が変わらないとき ⇒「記載金額のない契約書」として200円の印紙税がかされる 増額契約の場合 ⇒増額部分のみが記載金額となる 減額契約の場合 ⇒「記載金額のない契約書」として200円の印紙税が課される |
*ポイント*
✅一通の契約書に売買契約と請負契約の記載がある場合、原則として、全体が売買契約に係る文書となる。
⇒両方の金額が記載されているときには、金額が高い方が記載金額となる。
✅契約書に、消費税額が区分記載されている場合には、消費税額は記載金額に含めない。
◆税率
印紙税の税率は次のとおりです。
| 記載金額がある契約書 | 記載金額に応じて異なる (ただし、記載金額が1万円未満の場合は原則非課税) |
| 記載金額がない契約書 | 200円 |
◆過怠税
印紙がはられていない場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額(つまり印紙税額の3倍)が過怠税として徴収されます。
また、印紙が貼られているものの、消印がない場合には、印紙の額面金額分の過怠税が徴収されます。
5. 固定資産税
不動産を保有している間は、毎年、固定資産税がかかります。
◆固定資産税の基本的な内容
固定資産税の基本的な内容
◎課税主体 *誰が税金を課すのか?
⇒不動産がある市町村(地方税)
◎納税義務者 *誰が税金を払うのか?
⇒賦課期日(1月1日)現在、固定資産税台帳に所有者として登録されている者
例えば ×2年1月1日現在、Aさんが所有している不動産を、2月1日にBさんに売却した、という場合、×2年度の固定遺産税の納税義務者はAさんとなる。
ただし、下記の場合は 以下の取り扱いとなる。
| ①質権が設定されている土地の場合 ⇒質権者が納税義務者となる |
| ②100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定された土地の場合 ⇒地上権者が納税義務者となる |
| ③災害等により所有者が不明な場合 ⇒市町村は賦課期日における使用者を所有者とみなして納税義務者にできる |
| ④市町村が相当な努力が払われたと認められる方法により探索を行ってもなお所有者の存在が不明な場合 ⇒市町村はその使用者を所有者とみなして納税義務者にできる |
◎課税客体 *何に対して税金がかかるのか?
⇒固定資産(土地、家屋、償却資産)に対して税金がかかる
償却資産⇒事業用の機械など、減価償却を行う資産
◎非課税 *税金がかからない場合は?
⇒所有者が国・地方公共団体等であるとき
◎課税標準 *税金の計算のベースとなる金額は?
⇒賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)
※原則として3年に1度、評価替えが行われる
◎税金の計算 *税率はいくら?
⇒固定資産=固定資産税評価額×1.4%
1.4⇒標準税率 *これをベースに市町村で税率を決めることができる
◎納付方法 *税金の納め方は?
⇒普通徴収
普通徴収とは、国や地方公共団体が税額を計算して、納税者に通知し、それにもとづいて納税者が税金を納付する方法
◆免税点
課税標準額が以下の場合には、固定資産税はかかりません。
免税点
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
◆課税標準の特例
住宅用地については、課税標準の特例があります。
課税標準の特例
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
⇒特例はこの部分を調整
| ①小規模住宅用地(住宅用地で一戸のうち200㎡以下の部分) |
| 固定資産税評価額×1/6 |
| ②一般住宅用地(200㎡の部分) |
| 固定資産税評価額×1/3 |
◆税額軽減の特例
一定の条件を満たした新築住宅については、税額軽減の特例があります。
税額軽減の特例
| 床面積が50㎡以上280㎡以下 (貸付用マンション・アパートの場合は40㎡以上280㎡以下)など |
新築住宅の場合で、一定の条件を満たしたときは、新築後、下期の期間、120㎡までの部分について税額が1/2に軽減される
通常⇒固定資産税=固定資産税評価額×1.4%が半分になるということ!
| 一般住宅 | 長期優良住宅 | |
| 3階以上の中高層耐火建築物マンション等 | 5年間 | 7年間 |
| 上記以外戸建て(2階以下) | 3年間 | 5年間 |
◆タワーマンションの特例
居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション。高さが60mを超える建築物のうち、複数階に住戸が所在しているもの)に対する固定資産税については、当該タワーマンション全体にかかる固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる各区分所有者の専有部分の床面積を、一定の補正率によって補正します。
※人の居住用に供する専有部分に限ります。
なお、専有床面積補正率は、タワーマンションの1階を100とし、階が1つ増すごとに、10/39を加えた数値となります。
◆固定資産の価格決定
①固定資産の評価・価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて、市町村の固定資産評価員が行います。
そして、固定資産評価員の評価にもとづいて、市町村が毎年3月31日までに固定資産の価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
②固定資産課税台帳
固定資産課税台帳のポイントは次のとおりです。
固定資産課税台帳のポイント
◆納税義務者等は、必要に応じて、市町村長に対して、自分の固定資産に関する部分の閲覧を請求することができる。
◆納税者は固定資産課税台帳の登録価格に不服があるときは、一定期間において、固定資産評価審査委員会に対して、文書によって審査の申し出をすることができる。
③土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿
市町村長は、毎年3月31日までに、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければなりません。
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿のポイント
◆市町村長は、毎年4月1日から
4月20日または最初の納期限の日のいずれか遅い日までの期間、納税者の縦覧に供さなければならない。
6. 所得税(譲渡所得)
◆所得税とは
所得とは、個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額をいい、この所得に対してかかる税金を所得税といいます。
所得の分類
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得
⑨一時所得 ⑩雑所得
◆譲渡所得とは
土地、建物、株式、ゴルフ会員権、書画、骨董品などの資産を譲渡することによって生じる所得をいいます。
◆譲渡所得の分類
土地・建物等の譲渡によって生じた所得(土地・建物等の譲渡所得)は所有期間が5年以内か5年超によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類される。
また、土地・建物等の譲渡所得の課税方法は分離課税に区分されます。
土地・建物等の譲渡所得
◎短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡
◎長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超の土地・建物等の譲渡
◆譲渡所得の計算
譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
【取得費の例】
譲渡した資産の購入代金、取得時の仲介手数料、登録免許税、不動取得税など
☆取得費が不明な場合、収入金額の5パーセントを取得費とすることができる
【譲渡費用の例】
譲渡時の仲介手数料・印紙税・取り壊し費用など
◆譲渡所得にかかる税率
土地・建物等の譲渡所得にかかる税率は次のとおりです。
譲渡所得にかかる税率
譲渡所得の税額=譲渡所得金額×税率
◎短期譲渡所得の場合⇒所得税:30パーセント 住民税:9パーセント
◎長期譲渡所得の場合⇒所得税:15パーセント 住民税:5パーセント
◆居住用財産の特例
居住用財産を譲渡等した場合で、一定の要件を満たしたときは、次の特例を受けることができます。
①居住用財産の3,000万円の特別控除
居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
この特例の主な内容は次のとおりです。
居住用財産の3,000万円の特別控除
(課税)譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円
| ポイント |
| 譲渡した居住用財産の所有期間が短期でも長期でも利用できる |
主な適用要件
⇒
☆居住用財産の譲渡であること
・現在居住している家屋・その敷地
・過去に居住していた家屋・その敷地
☆配偶者、直系血族、生計を一にしている親族等への譲渡ではないこと
☆前年、前々年にこの特例を受けていないこと
☆譲渡年、前年、前々年に居住用財産の買い替えの特例等を受けていないこと
②収容等の5,000万円の特別控除
収容等によって、土地や建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額から最高5,000万円を控除することができます。
収容等の5,000万円の特別控除
譲渡所得の金額=総収入金額-取得費+譲渡費用)-5,000万円
| ポイント |
| 譲渡した資産の所有期間が短期でも長期でも利用できる |
主な適用要件
☆土地収用法、都市計画法にもとづいて資産が収容等され、保障金額等を受け取っていること
☆最初に買取等の申し出があった日から6か月を経過した日までに譲渡されたものであること
☆公共事業の施工者から最初に買取等の申し出を受けた者による譲渡であること
③低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等であることについての市区町村長の確認がされたものを譲渡したときは、その年中の低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の金額から最高100万円を控除することができます。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-100万円
| ポイント |
| 譲渡した資産の所有期間が長期であるもののみ利用できる |
| 譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は適用対象外 |
主な適用要件
☆低未利用土地等であることについて、市町村長の確認がされたものであること
☆その年の1月1日における所有期間が5年越えであること
☆その低未利用土地が都市計画区域内にあること
☆譲渡価格がその上にある建物等を含めて500万円以下であること
④居住用財産の軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年越の居住用財産を譲渡した場合、①または②の特別控除後の金額(ただし6,000万円以下の部分)について10パーセントの軽減税率が適応されます。
※6,000万円を超える部分については、長期譲渡職の税率15パーセントが適用される
⑤優良住宅の軽減税率の特例
優良住宅地の造成等のために、国や地方公共団体等に対して所有期間が5年越えの土地等を譲渡した場合、譲渡益(ただし2,000万円以下の部分)について10パーセントの軽減税率が適用されます。
⑥空き家にかかる3,000万円の特別控除の特例
相続の開始の直前において、被相続人の居住用であった家屋で、その後空き家になっていた家屋を一定期間内に譲渡した場合は、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
空き家にかかる3,000万円の特別控除の特例
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円
※相続人が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円
| ポイント |
| 相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例と選択適用となる |
主な適用要件
☆相続開始まで被相続にの居住用に供されていて、その後、相続によって空き家になったこと
※家屋を取り壊したあとに敷地を売却する場合も適用できる
☆1981年5月31日以前に建築された家屋であること
☆マンションなど区分所有建物でないこと
☆相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したこと
☆譲渡対価が1億円以下であること
◆住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
①住宅借入金等特別控除とは
住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増改築した場合には、住宅ローンの年末残高に一定の率をかけた金額について税額控除を受けることができます。この制度が住宅借入金等特別控除です。
②控除対象借入限度額、控除率、控除期間
住宅ローン控除の控除対象借入限度額は、控除率、控除期間は以下のとおりです。
なお、①40歳未満で配偶者を有する人、②40歳以上で40歳未満の配偶者を有する人③19歳未満で扶養親族を有する人のいずれかに該当する人を子育て特例対象個人といい、子育て特例対象個人が認定住宅等の新築等をして居住した場合には、控除限度額が上乗せとなります。
控除対象借入限度額、控除率、控除期間(新築の場合)
| 住宅ローン年末残高限度額 | 控除率 | 控除期間 | |
| 認定長期優良住宅低炭素建築物 | 4,500万円 子育て特例対象個人は5,000万円 |
0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 子育て特例対象個人は4,500万円 |
0.7% | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 子育て控除対象個人は4,000万円 |
0.7% | 13年 |
| その他住宅 | 0円 2023年までに建築確認を受けた住宅などは 2,000万円 |
0.7% | 10年 |
③適用要件
住宅借入等特別控除の主な適用要件は次のとおりです。
住宅借入金等特別控除の主な適用要件
◆返済期間は10年以上の住宅ローンであること
◆原則、住宅を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること
◆控除を受ける都市の合計所得金額が2,000万円以下であること。ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、合計所得金額が1,000万円以下の者に限る
◆住宅の床面積が50㎡以上(一定の場合は40㎡以上)であること
◆床面積の半分以上の部分が自分で居住するためのものであること
◆居住年、前二年、後三年に以下の特例を受けていない事
⇒・居住用財産の特別控除
・特定居住用財産の買い替えの特例
・居住用財産の軽減税率の特例など
7. まとめ
不動産は高額な資産であると同時に、多くの税金が関わってきます。
「買う」「持つ」「売る」「引き継ぐ」それぞれのステージで異なる税金が発生するため、正しい知識を持ち、計画的に行動することが大切です。
税制は毎年見直されることもあるため、常に最新情報をチェックしつつ、専門家のアドバイスを受けながら無理のない不動産活用・資産形成を目指しましょう。
※本記事は2025年7月26日時点の内容です。
執筆者名:丸山不動産販売 編集部
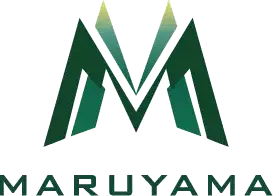
丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。
お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが
プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!
是非お気軽にご相談ください!
ページ作成日 2025-07-26
- 空家を放置するとどうなる?罰則の内容と売却を検討すべきタイミングを解説
- 建築条件付きの土地は売却できる?売却活動を成功させるための5つのステップ
- 【奈良市 不動産売却】相場を知って後悔しない売却をする方法
- 空家の不動産売却はいつがベスト?タイミングと売却時期の判断ポイント
- 「親の家を売るなんて…」迷ったあなたへ。相続不動産で後悔しない選択とは?
- 奈良の不動産購入で「失敗しない」ための完全ガイド!流れと注意点を徹底解説
- 「まだ売れない…」と悩むあなたへ:不動産売却が長引く理由を徹底解説!最適な売却時期とタイミングを見極める方法
- 【奈良県で売却】不動産売却のタイミングと売却時期を徹底解説!スムーズな取引を実現するステップガイド
- 奈良市の不動産会社が解説!不動産の売却時期はいつがベスト?住み替えを後悔しないためのタイミング戦略
- 【奈良県の不動産売却】失敗しない不動産売却「売却時期」と「タイミング」
- もっとみる
| << | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 2026年02月(0)
- 2026年01月(5)
- 2025年12月(4)
- 2025年11月(4)
- 2025年10月(3)
- もっとみる

 0742-93-6000
0742-93-6000