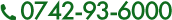「離婚」で損しない!不動産売却の最適な「タイミング」と注意すべき「売却時期」 | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売
「離婚」で損しない!不動産売却の最適な「タイミング」と注意すべき「売却時期」

離婚という人生の大きな転機において、自宅という高額な資産の処分は、精神的にも金銭的にも大きな負担となります。
しかし、その「心理的な焦り」や「手続きの知識不足」が原因で、本来得られたはずのお金を失っているケースが非常に多いのが現実的です。
本コラムでは、できるだけ損をしない最適な「タイミング」と注意すべき「売却時期」について、わかりやすく解説していきます。
1.はじめに:離婚時の不動産売却で「損」をする人が多い理由
離婚による、不動産売却では、本来得られたはずのお金を失っているケースが非常に多いのが現実です。
なぜ、損をしてしまうのでしょうか?
主な理由は次の3点です。
「一刻も早い関係を断ちたい」という感情が、冷静な市場分析や売却準備を妨げ、結果的に安値での売却につながる。
不動産における「タイミング」と「売却時期」の違い、そしてそれが税金(譲渡所得税)に与える影響を知らない。
財産分与や住宅ローンに関して、夫婦間で十分に合意形成できていないため、手続きが停滞し、売却時期を逸してします。
本コラムでは、これらの「損をする要因」を徹底的に排除するため、離婚が決定してから実際に自宅を売却するまでの「最適なタイミング(手続きの前後)」と、「注意すべき売却時期(税制上の有利・不利)」を詳細に解説します。
最後までお読みいただくことで、あなたは金銭的な後悔のない、円満な次のスタートを切るための知識を手に入れることができるでしょう。

2.〈基礎知識〉離婚時の不動産売却の仕組みとゴール
離婚時に伴う不動産売却は、単なる「家の売買」ではなく、「財産分与」という法的な手続きがセットになります。
この仕組みを理解することが、「損をしない」ための第一歩です。
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は、名義がどちらにあろうと「共有財産」と見なされます。
この共有財産を離婚時に公平に分け合うのが「財産分与」です。
不動産の場合、その価値(時価からローン残債を引いた純資産)を原則として2分の1ずつに分与します(清算主義)。
不動産を売却する場合、この2分の1を公平に分けることがゴールとなります。
【財産分与の具体的な例】
ケース①:自宅を売却し、売却代金を夫婦で分ける
▼状況
〇家:夫婦共有名義(持ち分:夫1/2、妻1/2)
〇住宅ローン:残債あり(残り1,500万円)
〇売却価格:3,000万円
▼財産分与の流れ
1.売却代金3,000万円
2.住宅ローン残債1,500万円を完済
3.残り1,500万円を夫婦で折半⇒各750万円ずつ分与
▼ポイント
〇最もシンプルな方法
〇現金化されるためトラブルが少ない
〇ローンが残る家でも完済できるかが重要
ケース②: 妻が家に住み続け、夫の持ち分を妻が買い取る
▼状況
〇家:夫婦共有名義(持ち分:夫1/2、妻1/2)
〇評価額:2,800万円
〇ローン残債:1,000万円(夫が主たる債務者)
▼財産分与の流れ
1.評価額2,800万円-ローン1,000万円
⇒純資産1,800万円
2.持ち分1/2ずつなので、夫の持ち分価値は900万円
3.妻が夫へ900万円を支払い、夫の名義を外す
4.住宅ローンは妻単独名義へ借り換え
▼ポイント
〇子供の学校の関係などで「住み続けたい」時によく使われる
〇ローンの借り換えができるかどうかが一番の壁
ケース③: 夫が住み続けるが、妻に代償金を支払う(住み続ける側が支払い)
▼状況
〇家:夫単独名義
〇評価額:2,000万円
〇ローン残債:800万円
〇妻は家に住まない
▼財産分与の流れ
1.評価額2,000万円-残債800万円
=純資産1,200万円
2.財産分与で妻に600万円支払う
▼ポイント
〇名義はそのままで、住み続ける側が現金を渡す方法
〇現金がない場合、借り換えや追加ローンで調整する
ケース④: ローン残債が家の評価額より高い(オーバーローン)の場合
▼状況
〇家の評価額:1,500万円
〇ローン残債:2,200万円(700万円のオーバーローン)
▼財産分与の考え方
〇家を売却しても700万円の借金が残る
〇誰が残債をどう負担するか話し合う
▼よくある分け方
〇夫婦で350万円ずつ負担
〇主たる債務者(例:夫)が全額負担し、妻は放棄
〇任意売却で整理して残債の支払い方法を調整
ケース⑤: 家は分与せず、他の財産で調整する
▼状況
〇家:夫単独名義
〇評価額:3,000万円
〇ローン残債:1,200万円
〇預貯金:夫婦合計1,000万円
▼財産分与の流れ
〇不動産は夫がそのまま取得
〇預貯金1,000万円を妻が800万円、夫が200万円受け取るなど(不動産の純資産1,800万円の半分に近くなるように調整)
▼ポイント
〇住み続ける側にとっても最もシンプル
〇他の資産が十分にある場合に選択される
不動産売却は、通常以下のステップで進み、売却代金は最終的に財産分与に充てられます。
1. 不動産の査定: まずは物件の現在の市場価値を知る。
2. 売却活動: 買主を見つけ、売買契約を締結する。
3. 決済・引き渡し:買主から売買代金を受け取る。
住宅ローン完済:代金からローンの残債を一括で返済し、抵当権を抹消する
4. 諸費用・税金の支払い: 仲介手数料、登記費用、譲渡所得税(利益が出た場合)などを支払う。
5. 残額の分与: 残った純資産を、夫婦間で取り決めた割合(通常は折半)で分け合う。
特に注意が必要なのが、住宅ローンが残っている場合です。
〇アンダーローン: 不動産の売却価格がローン残高を上回るケース。
売却代金で完済し、残った利益(純資産)を分与できます。
〇オーバーローン: 不動産の売却価格がローン残高を下回るケース。売却してもローンを完済できないため、夫婦で不足分をどのように負担するかを話し合わなければなりません。
これが離婚時の売却を最も複雑にする要因の一つです。

3.最適な「タイミング」:「離婚前」VS「離婚後」のメリット・デメリット
ここでいう「タイミング」とは「離婚届を提出する前後、どちらの時期に売買契約を締結するのが有利か」という、手続き上の判断を指します。
税制上の有利不利も関わってくるため、非常に重要な選択です。
▼「離婚前」に売却するメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 手続き | 夫婦間の協力が得られやすく、手続きがスムーズに進みやすい | 感情的な対立が売却交渉に影響を与え、価格交渉が難航する可能性がある。 |
| 税制面 | 居住用不動産の「3,000万円特別控除」が適用しやすい ※1 |
夫婦のどちらも、売却利益にかかる税金を軽減できる可能性が高い |
| ローン | 夫婦協力して残債処理を行いやすい | 契約書や登記簿に双方の名前が残るため、印鑑証明や実印の手配など、協力が不可欠 |
| 金銭面 | 売却後の現金を財産分与の対象にできるため、公平な分与がしやすい | 売却完了前に離婚届を出してしまうと、あとから分与トラブルになりやすい |
※1:「3,000万円特別控除」とは、マイホームを売却して利益が出た場合、3,000万円まで税金がかからないという特例です。この特例は、離婚前に夫婦の共有財産として売却するほうが適用しやすくなります。
▼「離婚後」に売却するメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 手続き | 完全に単独名義になっていれば、配偶者の協力なしで売却活動を始められる。 | 連絡が取りづらくなり、実印や署名が必要な場面で手続きが頓挫しやすい。 |
| 税制面 | 財産分与として取得した不動産には、特例の適用が難しくなる場合がある。 | 譲渡所得が発生するリスクが高まる |
| ローン | 住宅ローンが残っている場合、残債の名義を一本化する必要があり、審査が厳しくなる。 | ローン名義変更ができない場合、売却自体が難しくなる。 |
| 金銭面 | 分与割合(通常は1/2)が明確になるため、売却の合意形成がスムーズ。 | 売却完了前に離婚届を出してしまうと、あとから分与トラブルになりやすい |

税制上の特例や、手続きの円滑さを考慮すると、原則として「離婚届を提出する前に、売買契約を締結する」ことが、金銭的な「損をしない」ための最善のタイミングとなります。
ただし、DVや精神的苦痛など、やむを得ない事情で一刻も早く離婚したい場合は、弁護士や専門の不動産会社に依頼し、離婚後の売却に向けた準備を整える必要があります。

4. 注意すべき「売却時期」:税金と特例を考慮したベストな選択
ここからは、「時期」、すなわち「どれくらいの期間、その不動産を所有していたか」や「いつ売却を完了させるか」が、税金に与える影響について深く掘り下げます。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
この税率は、不動産の所有期間によって大きく変わります。
| 所有期間 | 区分 | 所得税・住民税の合計税率 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
不動産を売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかで、税率が約2倍も違ってきます。
【具体的な注意点】
● 離婚時の焦りから、所有期間が5年未満で売却してしまうと、利益に対して短期譲渡所得の高い税率が適用され、手取りが大きく減少する可能性があります。
● もし所有期間が4年半程度であれば、半年待って5年超になってから売却決済を行うだけで、税率が半分近くになり、「損をしない」どころか、大きな利益につながる可能性があります。
前章でも触れた通り、マイホームを売却して利益が出た場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
これが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
離婚時の売却でこの特例を適用するためには、特に以下の要件を満たす必要があります。
● 自分が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
● 「居住用」として使用されていた不動産であること。
【離婚時の特例適用の注意点:財産分与と控除】
● 離婚前に売却し、売却代金を分与する場合: 夫婦の双方が特例の適用を受けられます。(各自3,000万円まで控除)
● 離婚後に財産分与により配偶者が不動産を取得し、その後に配偶者が売却する場合
①分与により取得した不動産には、分与を受けた側(売却する側)が住んでいなくても特例を適用できる可能性があります。
ただし、離婚成立から3年以内に売却を完了させる必要があります。
②この特例を適用するためには、売却する側が「元居住者」としての要件を満たしている必要があります。
手続きが複雑になるため、必ず税理士に相談が必要です。
離婚後の売却は、特例を適用できる期限が「3年以内」と設定されています。もし離婚後4年目に売却したとしても、特例は適用できず、税金負担が重くなり「損」をしてしまうのです。
不動産売却で利益(譲渡所得)が出なかった場合、つまり売却しても手元にお金が残らない、あるいはローン残債のほうが多くて持ち出しになるケースでも、「損をしない」ための税制上の救済措置があります。
| 特例名 | 適用条件 | メリット |
| 居住用財産の買い替え特例 | 売却した不動産の代金で新しいマイホームに買い替える場合 | 利益が出ても課税を将来に繰り延べられる。 |
| 居住用財産の譲渡損失の繰超控除 | 売却によって損失が出た場合(特にオーバーローンの場合) | 損失を翌年以降最大3年間にわたり他の所得から差し引くことができる。 |
離婚に伴い、どちらか一方が新しい住居を購入する場合、買い替え特例が有利に働くことがあります。
また、オーバーローンで泣く泣く売却することになったとしても、譲渡損失の繰越控除を適用できれば、今後の所得税・住民税が軽減され、金銭的なダメージを和らげることが可能です。
【重要:売却時期の結論】
最高の売却時期とは、「所有期間が5年超になった直後」かつ、「3,000万円特別控除の適用期限(主に離婚後3年以内)が来る前」の時期であると言えます。この時期を逃さないことが、「損をしない」売却時期の決定打となります。
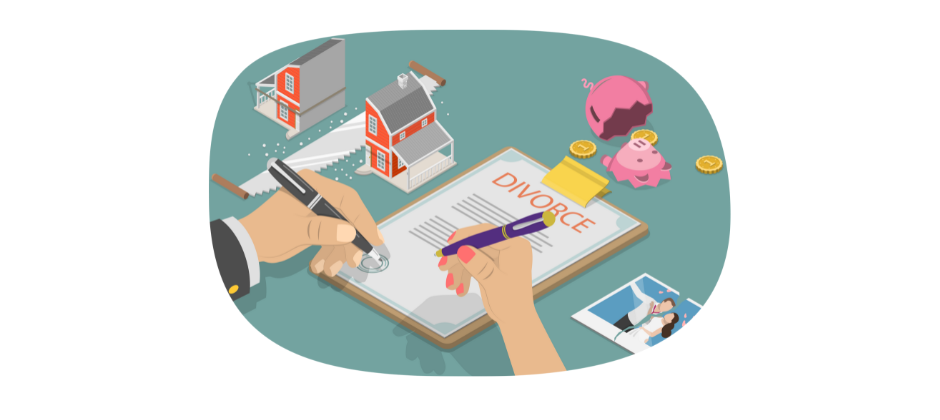
5. 【ケース別】ローン残債と名義の状況別「損をしない」ための戦略
不動産売却の難易度は、住宅ローンの残債状況と、不動産・ローンの名義がどうなっているかによって大きく異なります。
ここでは、ケース別の最適な戦略を解説します。
1.アンダーローンの場合(売却代金>ローン残債)
【戦略】売却代金でローンを完済できるため、最もシンプルなケースです。
〇 最優先事項:「売却時期」の節税対策を徹底する(4章で解説した5年超・3,000万円控除の適用)
〇 名義人の対応:共有名義の場合は、売買契約書に夫婦双方の署名捺印が必要です。
離婚が泥沼化していても、この手続きのために協力し合うことが必須となります。
2.オーバーローンの場合(売却代金<ローン残債)
【戦略】売却してもローンが残るため、この残債の処理が「損をしない」ための最大の焦点です。
〇 対策A:残債を現金で補填し任意売却:夫婦の貯蓄などで不足分を補い、通常の売却(任意売却ではない)として進める。
ポイント:誰がどれだけ不足分を負担するかを、離婚協議で明確に取り決めること。
〇 対策B:任意売却を検討:住宅ローンを借りている金融機関の合意を得て、市場価格に近い価格で売却する方法。
ポイント:金融機関は残債を帳消しにはしてくれません。残債の返済計画(いくらずつ、いつまで返済するか)を金融機関と交渉する必要があります。
この交渉が今後の生活に直結するため、任意売却に強い専門の不動産会社を選ぶことが絶対条件です。
〇 重要な税制:譲渡損失の繰越控除を忘れずに申請し、残債の負担による金銭的なダメージ税金面から軽減する。
3.片方が住み続ける場合(代償金で分与)
【戦略】不動産を売却せず、一方が住み続け、その代わりに住まない側へ家の価値の半額(代償)を支払うケース。
〇 最優先事項:ローンの名義変更または借り換え(リファイナンス)
住み続ける側が単独でローンを組めるよう、金融機関の審査を通過する必要があります。
元の名義人にローンの支払い義務が残ったまま離婚すると、元配偶者の返済が滞った場合に自分の信用情報に傷がつくという「損」が生じます(連帯保証人の解除も必須)
〇 代償金の算定:不動産の適正な時価を把握するため、複数の不動産会社に査定を依頼し、公平な金額を算出すること。
4.共有名義の不動産と連帯債務・連帯保証
不動産の名義が共有、かつローンが連帯債務(夫婦それぞれが債務者)または連帯保証(一方が主債務者
、もう一方が保証人)になっている場合、離婚しても自動的に債務や保証から解放されるわけではありません。
〇 絶対にしてはいけないこと:勝手に名義変更だけ行い、ローン契約はそのまま放置すること。
〇 損をしないための対応
1.売却して完済する(最もシンプルで確実)
2.住み続ける側がローンを借り換えることで、元配偶者を債務・保障から完全に外す。
これらの対応ができない場合、「離婚したのに元配偶者のローンのせいで自分の新しい生活に支障が出る」という、金銭的・精神的な「損」を被ることになります。

6. 売却を円滑に進めるための重要チェックリストと専門家の選び方
離婚時の不動産売却を成功させる鍵は、「感情論」を排し、「プロの知恵」を借りて迅速に進めることです。
1. 売却前に夫婦で合意すべき重要チェックリスト
売却活動に入る前に、以下の5点を必ず書面で合意し、離婚協議書(公正証書推奨)に残してください。
〇 売却決定の合意: 不動産を売却すること自体に合意しているか。
〇売却価格: 最低売却価格を設定するかどうか(安売りを防ぐ)。
〇売却活動の主導権: 誰が不動産会社とのやり取りを行うか。
〇売却経費の負担割合: 仲介手数料、登記費用などの諸費用をどう分けるか。
〇売却益(残金)の分与割合と支払時期: 代金の入金後、いつまでに、どう分けるか。
2. 「損をしない」ための専門家選びのポイント
離婚案件に不慣れな不動産会社や士業に依頼すると、手続きの遅れや税制上の見落としにより「損」をする可能性があります。
| 専門家 | 役割 | 選ぶ際のポイント |
| 不動産会社 | 不動産の査定、売却活動、買主の交渉 | 「離婚案件の売却実績」が豊富か。 「任意売却」の経験があるか。 |
| 弁護士 | 財産分与の交渉、離婚協議書の作成 | 不動産分野に理解があり、感情論ではなく資産の清算を重視してくれるか。 |
| 税理士 | 譲渡所得税の計算、特例の適用 | 離婚に伴う、3,000万円特別控除や譲渡損失の繰越控除に詳しいか。 |
特に不動産会社は、単に価格が高い査定額を出す会社ではなく、「離婚による売却に理解があり、手続きを迅速かつ正確に進めてくれる会社」を選ぶことが「損をしない」ための最も重要な選択となります。
地域密着の当社の売却実績はコチラ。

7.【実際にあったトラブル事例】【よくある質問】
事例①:ローン残債が多い家を“オーバーローン”で売却したケース
状況
〇夫名義でローン残高 2,600万円
〇市場価格は 2,300万円
→ 300万円のオーバーローン
離婚し別々の生活を始めたいが、家を売らなければ前に進めない状態。
対応
〇 不足分300万円を夫婦で150万円ずつ負担して完済
〇 早期売却し、住み替え費用を確保
ポイント
〇離婚によって家に住む人がいなくなるため、多少価格を下げてでも早期売却を優先
〇 銀行との調整を不動産会社が間に入りスムーズに完了
事例②:奥様が住み続ける予定が、維持費が払えず売却へ変更
状況
〇親権は妻
〇子どもの学校区を変えたくないため、妻が家に住み続ける予定
〇夫が住宅ローンを支払い続ける「名義は夫、住むのは妻」の状態
2年後にトラブル発生
〇夫が再婚し、ローン負担が難しくなる
〇妻も固定資産税などの負担が大きい
→ 最終的に売却を決断
結果
〇 売却益約300万円が発生
〇150万円ずつ分けて、それぞれの生活費に充当
ポイント
〇“名義と実際の居住者が違う”と後々トラブルになりやすい例。
〇離婚時に「将来の負担」を具体的に決めておくべき。
事例③:財産分与割合で揉めたが、訪問査定で解決
状況
〇家の名義:夫婦の共有(夫60%、妻40%)
〇売却を決めるが「売却益をどう分けるか」で揉める
問題点
〇 査定額に差があり、夫婦で納得できなかった
〇不動産会社によって価格が300万円も違った
対応
〇中立的な第三者として「不動産鑑定士」に評価を依頼
〇 その金額で合意し売却
結果
鑑定価格に基づき、持分割合で財産分与
〇双方が合理的だと納得しスムーズに離婚成立
事例④:DVが絡み、急いで売却して転居資金を確保したケース
状況
〇妻が避難のため子どもを連れて別居
〇財産分与や連絡手段の調整が非常に困難な状態
〇夫は売却に協力的ではなかったが、弁護士介入で手続き可能に
対応
〇弁護士+不動産会社の連携で、安全に手続きを進める
〇相場よりやや低めでスピード売却
〇売却益は子どもの生活費・引越し費用に
ポイント
〇通常よりもプライバシー保護や連絡調整が重要。
〇こうしたケースでは「弁護士+不動産会社のタッグ」は必須

▼Q1. 家の名義が夫(妻)になっている場合、私は売却できますか?
売却には 所有者全員の同意 が必要です。
名義人が夫だけなら、妻だけでは売却できません。
逆に、共有名義の場合は 全員の署名・押印・身分証 が必要です。
▼Q2. 相手が売却に協力してくれない場合、どうしたらいいですか?
〇弁護士を通して話し合う
〇調停で売却を決める
〇家裁で「財産分与の対象」と認定し売却を進める
などの手段があります。
実務では 弁護士+不動産会社の連携 が最もスムーズです。
▼Q3. 住宅ローンが残っていても売却できますか?
可能です。
売却価格でローンが完済できない場合は オーバーローン(任意売却) の手続きを利用します。
銀行との交渉は不動産会社が代行できるので、まずは相談するのがおすすめです。
▼Q4. 売却代金はどのように分けるのですか?
一般的には
〇共有名義 → 持分割合に応じて分ける
〇単独名義 → 夫婦の話し合い(財産分与)で分ける
ただし、ローンの負担状況や頭金をどちらが出したかなど、事情により変わることがあります。
▼Q5. 住んでいる状態でも売却できますか?
可能です。
離婚の売却では「別居前に売りたい」という相談も多いため、 居住中のまま売却を進めるケースはよくあります。
▼Q6. 売却額は戸籍や相手に知られますか?
基本的に
〇契約書
〇精算書
などの書類は 名義人に渡る ため、まったく知らせずに売ることはできません。
ただし、住所を知られたくないなどの事情がある場合は、 弁護士や代理人を通して受け渡すことができます。
▼Q7. 売却益(譲渡所得)に税金はかかりますか?
売却して 利益が出た場合 は税金(譲渡所得税)がかかる可能性があります。
ただし、マイホームには3,000万円の特別控除 が使えるケースも多く、実際には“税金がかからない”ことが多いです。
離婚でも条件が合えば控除は使用できます。
▼Q8. 子どもの学校区を変えたくないのですが、売却はできますか?
住み続けながら売却することも可能ですし、 「買取」であれば退去時期の調整もしやすいです。
また、売却後に賃貸として借りる(リースバック)という選択肢もあります。
▼Q9. 離婚前と離婚後では、売却のメリットは変わりますか?
変わります。
離婚前のメリット 住宅ローンの手続きがラク 名義変更のトラブルが少ない 夫婦双方が協力しやすい
離婚後のメリット
〇売却益を財産分与しやすい
〇話し合いがまとまらない場合は調停に持ち込みやすい
〇連帯保証人問題が解消しやすい
▼Q10. 売却を急ぎたいのですが、どれくらいの期間が必要ですか?
〇仲介での売却:2〜3ヶ月が一般的
〇急ぐ場合:1〜2週間で「不動産会社の買取」が可能
離婚の売却では、 「早く現金化したい」「早く別居したい」などスピードが求められるため、 買取でのご相談が増えています。

8. まとめ 「損しない」ための究極の結論
離婚」に伴う「不動産」の「売却」において、「損をしない」ための究極の結論は「最良のタイミングと時期を逃さずに、専門家の力を借りて迅速に実行すること」に集約されます。
| 要素 | 最適な選択 | 損をしないための行動 |
|---|---|---|
| タイミング (手続き) |
原則「離婚届提出前」の売買契約締結 | 離婚協議で売却の合意を書面にお残す。 |
| 売却時期 (税制) |
「所有期間5年超」かつ「3,000万円控除の期限内」 | 契約前に税理士に相談し、性格な税率を把握する。 |
| ローン・名義 | 売却代金で完済、またはローンを借り換えて名義を一本化 | 元配偶者の債務・保証から完全に解放される |
| 実行 | 離婚に強い不動産会社・弁護士・税理士のチームを組む | 感情論を排除し、プロの冷静な判断に従う。 |
後悔しないために、準備と冷静さを 離婚時の不動産売却は、感情とお金、法律が複雑に絡み合う問題です。
しかし、しっかりと準備し、冷静に選択肢を見極めれば、将来的な後悔を防ぐことができます。
名義・ローンの確認と整理売却か保有かの明確な判断適切な査定と売却戦略税金・法的リスクへの備え専門家の協力と信頼できるパートナー選び 「感情を整理すること」と「資産を整理すること」は別問題です。
冷静な判断と適切な対応で、新しい一歩を踏み出しましょう。
執筆者名:丸山不動産販売 編集部
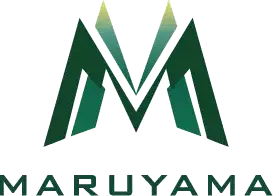
丸山不動産販売では、奈良県内の不動産購入、売却、建築などに対応しております。
お客様の住宅に関する決断を、業界経験豊富なスタッフが
プロフェッショナルとして誇りと責任感を持ち、丁寧にサポートいたします!
是非お気軽にご相談ください!
ページ作成日 2025-11-23
- 空家を放置するとどうなる?罰則の内容と売却を検討すべきタイミングを解説
- 建築条件付きの土地は売却できる?売却活動を成功させるための5つのステップ
- 【奈良市 不動産売却】相場を知って後悔しない売却をする方法
- 空家の不動産売却はいつがベスト?タイミングと売却時期の判断ポイント
- 「親の家を売るなんて…」迷ったあなたへ。相続不動産で後悔しない選択とは?
- 奈良の不動産購入で「失敗しない」ための完全ガイド!流れと注意点を徹底解説
- 「まだ売れない…」と悩むあなたへ:不動産売却が長引く理由を徹底解説!最適な売却時期とタイミングを見極める方法
- 【奈良県で売却】不動産売却のタイミングと売却時期を徹底解説!スムーズな取引を実現するステップガイド
- 奈良市の不動産会社が解説!不動産の売却時期はいつがベスト?住み替えを後悔しないためのタイミング戦略
- 【奈良県の不動産売却】失敗しない不動産売却「売却時期」と「タイミング」
- もっとみる
| << | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 2026年02月(0)
- 2026年01月(5)
- 2025年12月(4)
- 2025年11月(4)
- 2025年10月(3)
- もっとみる

 0742-93-6000
0742-93-6000